- システム開発の外注(発注)を成功させるための準備チェックリスト
- システム開発を外注する前に必ず押さえたい基本と準備の考え方
- システム開発を成功に導く外注チェックリストと実践ノウハウ
システム開発を外注する際には、事前の準備がプロジェクト成功のカギとなります。本記事では、システム開発の外注(発注)にあたって必要な準備項目をチェックリスト形式で解説します。専門知識がない方でもわかるようにシンプルな言葉でポイントをまとめました。このチェックリストを活用して準備を進めれば、外注先との開発をスムーズに進め、トラブルを防ぐことができます。
Contents
システム開発の外注とは?
システム開発の外注とは、自社内に開発チームを持たずに外部の専門会社やフリーランスに開発業務を依頼することです。近年、IT人材不足の解消策や専門性の高い開発ニーズに応える方法として外注が広く利用されています。まずは外注のメリット・デメリットを理解し、どのような場合に外注すべきかを見ていきましょう。
外注のメリット
- コストを抑えられる: 自社でエンジニアを採用・育成する費用や時間を省けます。必要な時だけ外部のプロに依頼できるため、固定人件費を削減できます。
- 専門知識を活用できる: 経験豊富な専門家に任せることで、高度な技術やノウハウをプロジェクトに取り入れられます。自社にないスキルを持つプロの力で、より高品質なシステム開発が期待できます。
- 開発スピードが上がる: 既に開発スキルを持つ外部パートナーに依頼するため、ゼロから人材育成するより早く開発が進みます。必要な作業に専念してもらえるので、タイトなスケジュールの案件でもスピーディーに対応してもらえるでしょう。
- 社内リソースを本業に集中できる: 開発業務を外注すれば、社内の人員は別の重要業務に専念できます。本来注力すべきコア業務にリソースを集中させつつ、システム開発は外部に任せる分業が可能です。
外注のデメリット
- コミュニケーションが難しくなる場合がある: 自社スタッフと外部開発者の間で意思疎通がうまくいかないと、要件の解釈違いや認識ズレが生じる恐れがあります。その結果、仕様の食い違いや納期の遅れが発生しかねません。密なコミュニケーションを取る工夫が必要です。
- 品質管理のリスク: 最初に要件を明確に伝えておかないと、出来上がった成果物が自社の期待と異なる可能性があります。外注先まかせにしすぎると、途中経過が見えづらく品質チェックが難しい場合もあります。事前に成果物の基準や受け入れ条件を定めておくことが重要です。
外注を選ぶべきタイミング
次のようなケースでは、システム開発を外注(発注)するのが効果的です。
- 社内に開発リソースが不足しているとき: 日常業務で手一杯で新規システム開発に充てる人材がいない場合や、担当できる人が社内にいない場合は外注を検討しましょう。
- 高度な専門知識が必要なとき: プロジェクトで特定の技術や専門スキルが求められるのに、自社メンバーにその経験がない場合、経験豊富な外部のプロに任せると安心です。
- 短期間でリリースする必要があるとき: 市場競争が激しい中で早くサービスを提供したい場合、外部リソースを活用することで開発スピードを上げられます。自社でチームを編成している間に機会を逃すより、外注によって迅速に開発を進める方が得策です。
なお、外注を検討する際は、どんなシステムを作りたいかを事前にしっかり整理しておくことが大切です。例えば、画面の一覧や画面遷移図、必要な機能のリストなどを作成しておけば、外注先とのやり取りが格段にスムーズになります。要件を明確化しておくことで、開発中の認識違いが減り、質の高いシステムを効率良く完成させられるでしょう。
外注と内製の違い
システム開発を「外注」する場合と「内製」(自社開発)する場合では、プロジェクトの進め方や得られるメリットが異なります。
- 外注 (アウトソーシング): 開発を外部の会社や個人に委託する方法です。自社に不足するリソースやスキルを補い、短期間で成果を出しやすいのが特徴です。特に最新技術を要するプロジェクトや大規模開発では、外注先の経験とスキルを活かすことで高品質なシステムを効率よく構築できます。ただし、外部とのやり取りや進捗管理に注意が必要です。
- 内製 (自社開発): 自社のチームでシステムを開発する方法です。社内にノウハウが蓄積され、開発過程で得た知見を今後も活かせるというメリットがあります。また、自社の裁量で開発を進めるため、仕様変更への柔軟な対応や長期的な運用もしやすいです。一方で、開発の各工程(設計・実装・テスト・運用)に精通した人材を確保・育成する必要があり、人件費や時間がかかる点は考慮しましょう。
どちらを選ぶかはプロジェクトの目的や状況によります。長期的にシステムを運用・改修していきたい場合や自社に十分な開発人員と知見がある場合は内製が向いています。逆に、短期間で成果を出したい場合や社内にない専門技術が必要な場合は外注を活用する方が効率的と言えます。自社のリソース状況や将来的な運用計画を踏まえて、外注と内製を使い分けましょう。
外注準備の重要性
システム開発を外注するにあたり、事前準備をしっかり行うことはプロジェクト成功の鍵です。準備の有無でプロジェクトの結果に大きな差が生まれます。ここでは、なぜ準備が重要なのかを確認し、準備不足が招くリスクを見ていきます。
なぜ準備が必要なのか?
外注プロジェクトで成功するためには、事前の段取りや計画が不可欠です。実際、十分な準備をしてから外注したケースと、ほとんど準備せずに外注したケースとでは、結果に明確な差が出ています。事前に要件を明確に定義し計画を立てておけば、外注先との認識ズレを防ぎ、効率よく開発を進めることができます。
成功例と失敗例
- 成功したケース: 「どのようなシステムを作りたいか」を詳細にまとめてから外注しました。具体的には、画面構成や機能一覧、画面間の遷移図などをあらかじめ整理し、外注先と共有しています。その結果、コミュニケーションがスムーズに行われ、納期内に高品質なシステムを完成させることができました。事前準備がプロジェクト成功の土台となった好例です。
- 失敗したケース: 準備不足のまま外注してしまったためにトラブルが発生しました。要件が曖昧な状態で進めた結果、開発中に何度も仕様変更が起こり、その度にコスト超過や納期遅延につながりました。さらに、外注先が要件を正確に理解できず、完成したシステムが当初の想定と異なるものになってしまいました。いずれも準備を怠ったことが原因です。
準備不足が招くリスク
準備を十分に行わないまま外注を開始すると、以下のようなリスクが発生します。
- 仕様変更の頻発: 要件が不明確なままだと、外注先は独自の解釈で開発を進めるしかありません。その結果、「こんなはずではなかった」という認識違いから仕様変更が繰り返され、コスト増大や納期の遅れに直結します。
- 期待外れの成果物: 外注先に要件や期待する水準が正しく伝わっていないと、完成したシステムが自社の期待と大きくずれる恐れがあります。「出来上がったものが使えない」など最悪の事態を招かないためにも、最初の段階で認識合わせをしておく必要があります。
このように、準備を怠るとトラブルが増え、プロジェクト全体に悪影響を及ぼしてしまいます。逆に、事前に手順や必要な人材・要件をしっかり検討しておけば、外注先との連携がスムーズになり、プロジェクト成功の確率が格段に高まります。
要件定義書の作成
外注の準備としてまず要件定義書を作成しましょう。要件定義書とは、開発するシステムに必要な機能や仕様を具体的にまとめた文書です。これを用意することで、外注先に「どんなシステムを作りたいのか」を正確に伝えられます。明確な要件定義書があれば認識のズレを防ぎ、スムーズに開発を進めることができます。
要件定義書をしっかり準備すれば、外注先に的確な指示を出せるだけでなく、後から生じがちな仕様変更を減らすことができます。結果として余計なコスト削減にもつながるため、システム開発を外注する際はまず要件定義書を用意することが成功への第一歩です。
要件定義書を作成する際のポイントは次の通りです。
- 機能要件と非機能要件を分けて書く: システムに必要な機能要件(システムが持つ具体的な機能。例:「ユーザー登録」「検索機能」など)と、非機能要件(性能やセキュリティなど、機能以外で満たすべき条件)を分けて整理します。分類して書くことで、抜け漏れを防ぎ理解もしやすくなります。
- 画面一覧や画面遷移図を用意する: システム内で必要となる画面をすべてリストアップした画面一覧や、各画面間の遷移関係を示す画面遷移図を作成します。これによりシステムの全体像を外注先と共有でき、完成形のイメージ違いを防ぐのに役立ちます。
- その他の必要な情報も記載: 可能であれば、ユーザーの種類や権限、入力・出力するデータ項目、他システムとの連携要件など、開発にあたって参考になる情報も盛り込んでおきます。情報は具体的であるほど外注先が正しく理解しやすくなり、後工程での手戻りを減らせます。
予算計画の立て方
システム開発の外注では予算計画も欠かせません。適切に予算を配分し、見積もり内容をしっかり確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。予算策定の際に押さえておきたいポイントを以下にまとめました。
- 開発・テスト・保守のバランス: 予算は大きく「開発費用」「テスト費用」「運用・保守費用」のカテゴリーに分けて検討しましょう。開発費用ばかりに目が行きがちですが、リリース後の運用や保守にかかる費用も忘れずに計画に含めることが大切です。開発後にもシステム改修やサーバ維持など費用が発生するため、プロジェクト全体を見据えてバランスよく配分します。
- 見積もりの根拠を確認: 外注先から提示された見積もりは、その根拠を必ず確認しましょう。例えば、「開発期間はどれくらいか」「必要な工数(人日)はどの程度か」など詳しく説明してもらうことで、過大見積もりや過小見積もりを防げます。また、1社だけでなく複数の外注先から見積もりを取り、金額や内容を比較することで相場感をつかむことも有効です。
- 隠れコストも考慮: 追加機能への対応費用や運用に伴う人件費など、表面に見えないコストも見落とさないようにします。開発中に仕様変更や新機能追加が発生すると追加費用がかかるため、あらかじめ全体予算の10~20%程度を予備費として確保しておくと安心です。また、リリース後のアップデート対応や保守にかかる費用も事前に見積もり、将来的な予算オーバーを防ぎましょう。
綿密な予算計画を立てておけば、余裕を持ってプロジェクトを進められ、不要な出費を避けることができます。資金面の不安を減らすためにも、最初にしっかり計画を練っておきましょう。
社内体制の整備
外注プロジェクトを成功させるには、社内の受け入れ体制を整えておくことも重要です。プロジェクト開始前に社内で準備しておくべきポイントを確認しましょう。
- プロジェクトチームの編成: 社内のプロジェクトチームを編成する際は、メンバーのスキルや役割のバランスを意識します。例えば、技術に詳しい人、進捗管理が得意な人、外部との調整がスムーズな人など、それぞれの強みを持つメンバーが揃うと理想的です。また、チーム全体をまとめるリーダーを明確に選出し、責任者を立てておきましょう。
- コミュニケーション窓口の明確化: プロジェクト中は社内外で多くの連絡が発生します。誰がどの問い合わせに対応するのか、窓口担当を事前に決めておくとスムーズです。「技術的な質問はAさんへ」「進捗の報告はBさんが対応」など役割を決めておけば、情報伝達ミスや対応漏れを防げます。
- 役割分担と責任範囲の明確化: 各メンバーの担当範囲と責任をはっきりさせておきましょう。「自分の仕事はどこまでか」が曖昧だと対応が遅れたり、問題発生時に責任の所在が不明確になったりします。分かりやすいルールを作って全員に共有し、誰が何をするのか明確にしておくことが大切です。
これらの点を事前に整えておけば、社内で無駄な混乱が生じにくくなり、プロジェクトをスムーズに進行させる土台ができます。言葉の通り「良い準備が良い結果を生む」ので、ひと手間かけて社内体制を整えましょう。
ベンダー選定のポイント
システム開発を外注する際、どのベンダー(開発会社)に依頼するかは非常に重要です。信頼できるパートナーを選ぶために、以下のポイントをチェックしましょう。
- 実績や専門性の確認: 候補となるベンダーのこれまでの開発実績を調べ、自社が依頼したい分野での経験や専門知識があるか確認します。過去に手がけたプロジェクトの規模や業種など具体的な事例を見せてもらうと安心です。それらの実績から、そのベンダーの得意分野や技術力を把握できます。
- 評判・口コミの調査: ベンダーの評判も事前に調べましょう。インターネット上の口コミや他社の導入事例、クライアントからの評価などが参考になります。もし周囲にそのベンダーを利用したことがある知人がいれば、直接感想を聞いてみるのも有効です。実際の利用者の声から、対応の良さや信頼性について貴重な情報を得られます。
- 提案内容と見積もりの比較: 複数のベンダーから提案書や見積もりを取り寄せ、内容を比較検討しましょう。価格だけでなく、提案された開発アプローチやサポート体制、想定スケジュールなども含めて総合的に判断します。一見似た内容でも各社で細かな違いがあります。自社のニーズに最も合ったパートナーを選ぶために、焦らず丁寧に比較することが大切です。
これらのポイントを踏まえてじっくりベンダー選定を行えば、信頼できるパートナーと出会えるはずです。慎重かつ入念に選定することで、プロジェクト成功への第一歩を踏み出しましょう。
システム開発の発注時に確認すべき契約ポイント
システム開発を外部に発注する際には、契約書の内容をきちんと取り決めておくことが重要です。契約書の作成は難しそうに感じるかもしれませんが、以下のポイントを押さえておけば大きなトラブルを防げます。特に次の3点は必ず確認・明記しましょう。
- 成果物の定義: 契約書には「どんなシステムや機能を納品してもらうのか」を具体的に記載します。曖昧な表現は避け、「システムが満たすべき条件や動作」を明確に定義しましょう。これにより、完成後に「思っていたものと違う」という行き違いを防ぐことができます。
- 納期と支払い条件: 納期(スケジュール)と支払い条件も契約書で取り決めておきます。「いつまでに何を完了させるか」というマイルストーンを具体的に記載しましょう。また、支払いのタイミングや金額(着手金・中間金・最終支払いなど)も明記し、金銭面の取り決めをはっきりさせておきます。納期と支払い条件を明確にしておくことで、お互いの認識を揃え安心して進められます。
- 保守・サポート体制: システム導入後の保守サポートについても契約に盛り込みます。具体的には、「不具合修正や質問対応をどこまで無償で行うか」「保守期間や追加費用はどうなるか」といった事項を事前に取り決めて明文化します。納品後にサポートが受けられず困ることのないよう、必要なサポート範囲を双方で確認しておきましょう。
契約書は双方の信頼関係を支える大切なツールです。不明な点があれば法務の専門家に相談しながら、納得のいく形で契約を締結してください。しっかりとした契約を結んでおけば、プロジェクトを安心して進めることができます。
外注後の運用とフォローアップ
システム開発が完了しても、運用開始前に確認しておくべきことがあります。リリース後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用を実現するために、適切なフォローアップ体制を整えておきましょう。以下の点をチェックします。
- テストと検収の徹底: システムが完成したら、本番運用に入る前に徹底的なテストを行います。開発者の想定通りに動作するか確認するのはもちろん、実際のユーザー目線で使い勝手を検証することも重要です。不具合やエラーがないか細部までチェックし、問題があれば開発者に修正を依頼します。また、契約通りの成果物になっているか検収(受け入れ確認)を十分な時間をかけて実施しましょう。検収はプロジェクト完了の最終ステップなので、妥協せず取り組むことが成功のカギです。
- トラブルシューティング体制: 運用開始後に万一トラブルが発生した場合に備え、対応体制を事前に決めておきます。例えば、システム障害が起きた際の連絡先や対処フローをあらかじめ周知しておきます。「どのような問題が発生したら誰に連絡するか」「バックアップや復旧手順はどうするか」などを整理し、関係者で共有しておきましょう。さらに、システムの利用マニュアルやトラブル対応手順書を用意しておくことで、実運用時の混乱を最小限に抑えられます。
これらを事前に準備しておけば、運用開始後に予期せぬ問題が起きても柔軟に対応でき、安心してシステム運用をスタートできます。リリース直後こそ慎重に確認を行い、万全の体制で本番環境に移行しましょう。
プロジェクト管理のポイント
外注したからといって開発を任せきりにせず、発注者側もプロジェクト管理に継続的に関与することが大切です。定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正することで、より良い成果につながります。進捗確認を円滑に行うためのポイントを紹介します。
- 定期ミーティングで状況共有: ベンダーとのコミュニケーションを継続するため、定期的に打ち合わせや進捗報告の場を設けましょう。スケジュールや成果物の達成状況を一緒に確認し、課題があれば早期に共有します。進捗報告の場では、ベンダー側からの質問や提案にもしっかり耳を傾けましょう。必要に応じてオンライン会議ツールやチャットを活用すれば、離れた場所からでも効率的に情報交換ができます。
- 課題の早期発見と改善: プロジェクトの途中で出てきた課題は先延ばしにせず、早めに洗い出して対策を検討します。定期報告の際に「うまく進んでいる点」「問題となっている点」を具体的に話し合いましょう。小さな問題でも見逃さず対応する習慣をつけることで、大きなトラブルを未然に防げます。解決策を考える際は、ベンダーと協力して柔軟に対応し、必要であれば計画の見直しも検討します。
このように定期的な進捗確認と改善を重ねることで、プロジェクトを予定通りに進めやすくなり、結果的に質の高いシステムを完成させることができます。外注先との良好な関係を保ちながら、プロジェクトを成功に導きましょう。
準備を成功させる秘訣(ツール活用)
最後に、準備作業を効率化し、より効果的に進めるためのツール活用について紹介します。適切なツールを使えば、情報の整理や共有がスムーズになり、準備にかかる手間を大幅に減らすことができます。以下に役立つツールの例を挙げます。
- プロジェクト管理ツール: 「Trello」や「Asana」などのタスク管理ツールは、プロジェクトのタスク割り振りや進捗の見える化に便利です。チーム全体で「誰が何を担当しているか」「各タスクが今どの段階にあるか」を一目で把握できます。複数のタスクを並行して管理する場合にも最適です。
- コミュニケーションツール: 「Slack」や「Microsoft Teams」などのチャットツールを活用すると、チームメンバー間で迅速な情報共有が可能になります。テキストチャットのほかファイル共有やビデオ会議機能も充実しており、メールに頼らずリアルタイムに連絡を取り合えます。こまめな情報交換によってミーティングの頻度を減らしつつ、円滑な意思疎通が図れるでしょう。
- ドキュメント共有ツール: 要件定義書や契約書など複数人で編集が必要な資料には、「Google Workspace」(Googleドキュメントやスプレッドシート)や「Notion」といったクラウドツールがおすすめです。インターネット上で文書を管理できるため、最新内容を常にメンバー全員が閲覧・編集できます。外出先からアクセスすることも可能で、情報の見落としやバージョン違いを防げます。
これらのツールをうまく活用すれば、準備段階の作業効率が格段に向上します。自社のプロジェクト規模やチームに合ったツールを選び、事前準備を着実に進めていきましょう。
まとめと次のステップ
システム開発の外注(発注)を成功させるには、何より事前の準備が欠かせません。 今回紹介したチェックリストの各項目を丁寧に進めることで、プロジェクトの土台が固まり、トラブルを未然に防ぐことができます。
準備段階でプロジェクトの目的やゴールを明確にし、要件を具体化すれば、開発プロセスは格段にスムーズになります。さらに、予算やスケジュールの計画を立て、想定されるリスクへの対応策を用意しておくことで、予期せぬ事態にも柔軟に対応できるようになります。また、関係者全員が同じビジョンを共有できるため、認識のズレや無駄な手戻りも減らすことができます。
大きなプロジェクトほど、このような入念な準備が成功の鍵になります。焦らず時間をかけて準備を進めることで、満足のいくシステムを完成させられるでしょう。まずは本記事のチェックリストに沿って自社プロジェクトの内容を整理してみてください。準備が整ったら、信頼できる外注先に相談し、プロジェクトを前進させましょう。丁寧に積み重ねた準備が、最終的に大きな成果となって返ってくるはずです。






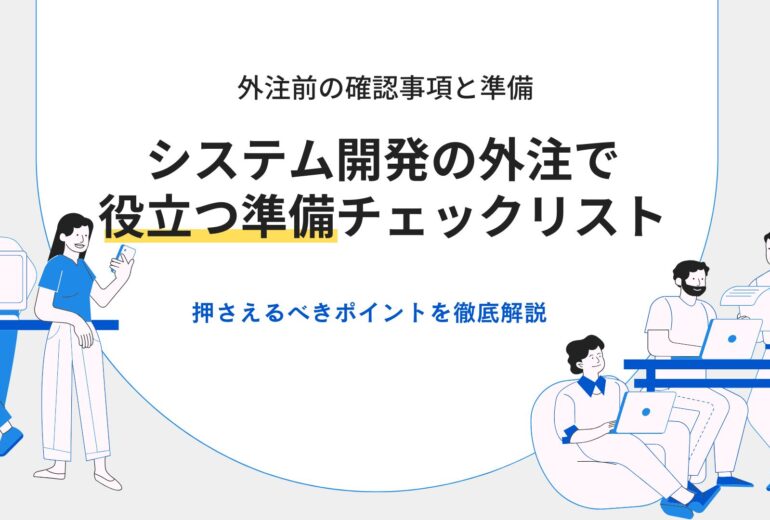
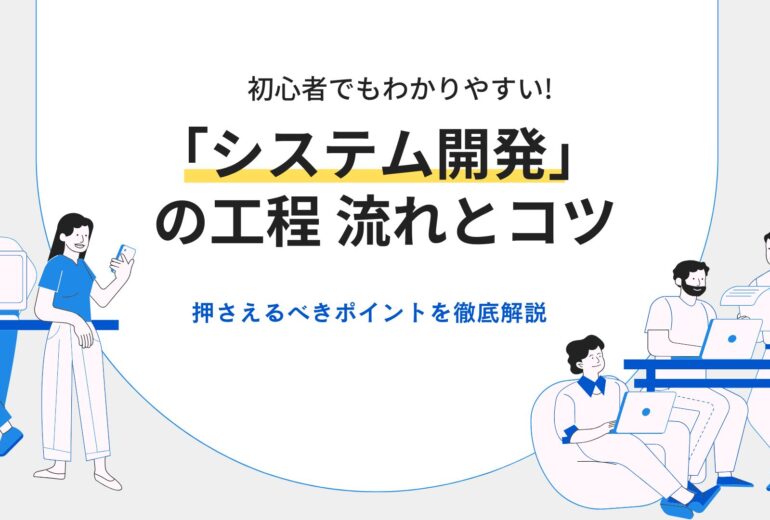
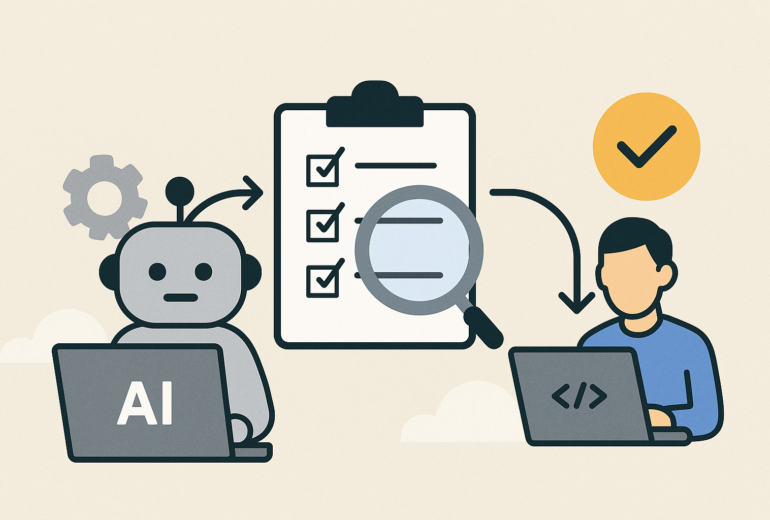



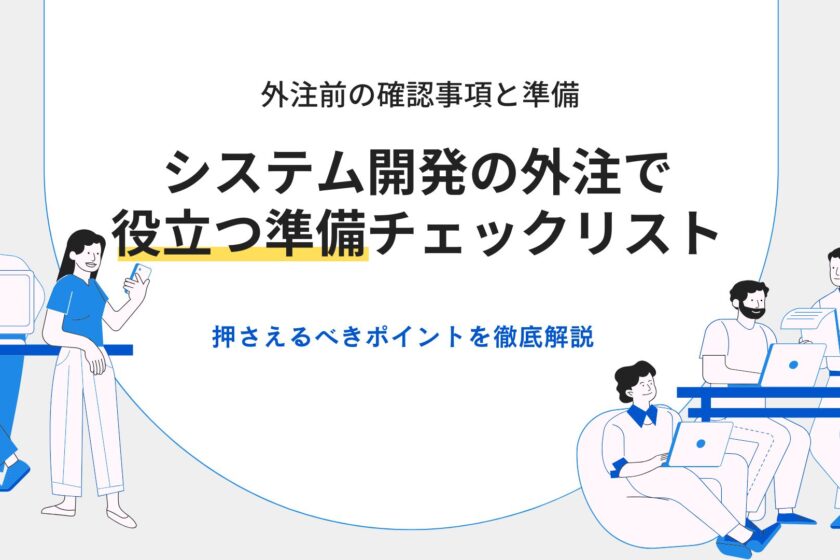



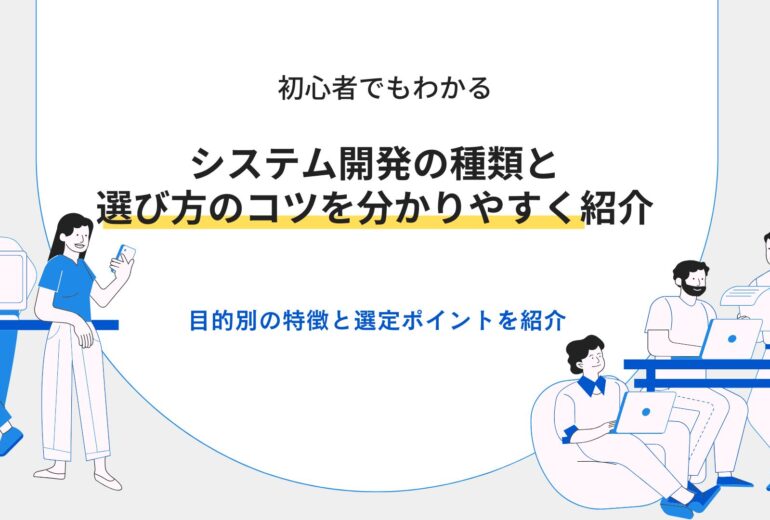
-770x520.png)
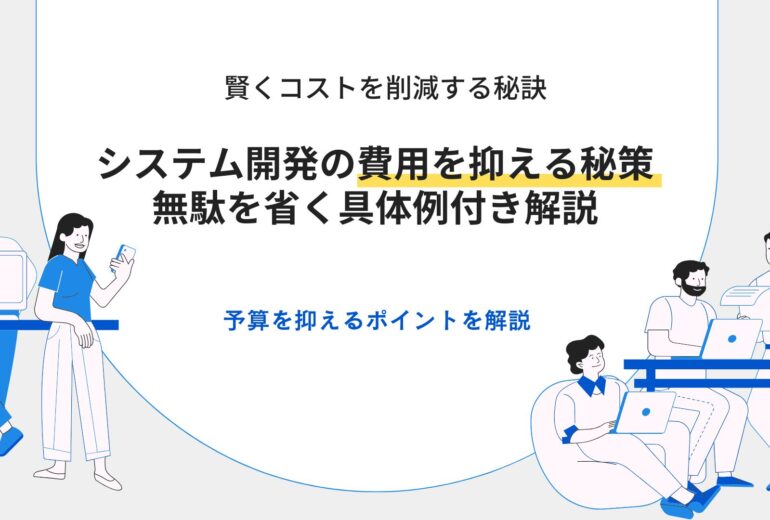

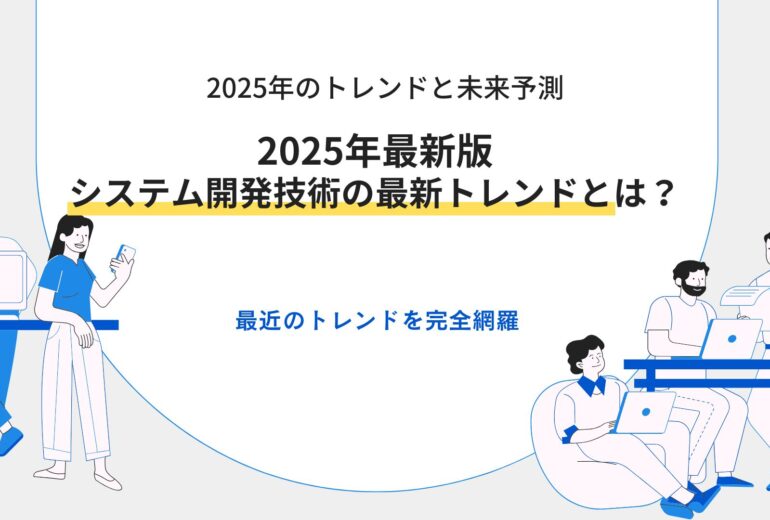



コメント