Contents
失敗学・アンチパターン:DX内製化で燃え尽きないために押さえたい体制・設計・採用のツボ
AIやクラウド、SaaSが一般化し、DX内製化にチャレンジする企業が一気に増えました。「ベンダーロックインから脱却したい」「自社の業務を深く理解したシステムをDX内製化で作りたい」といった期待は、ごく自然なものです。一方で、実務の現場では、DX内製化プロジェクトが途中で失速したり、担当チームが燃え尽きてしまう内製化 失敗の話も、同じくらい耳にします。最初は熱量高くスタートしたのに、数年後には開発体制が崩れ、システムは中途半端なまま…というパターンは決して珍しくありません。
本記事では、そうした内製化 失敗の表面的なエピソードではなく、その裏側にある「構造」に焦点を当てます。キーワードは体制・設計・採用です。DX内製化がうまくいくかどうかは、個々のエンジニアのスキルというより、開発体制の組み方、どのような前提でアーキテクチャを設計したか、そしてどのような人材戦略を描いたかに左右されます。DXの内製に関わるDX推進責任者や情報システム部門、現場マネージャーの方が、今の自社の状況を冷静に見直すための「判断基準」としてお読みいただければ幸いです。
なお、ここで扱うのは「こうすればDX内製化は必ず成功する」という万能の正解ではありません。重要なのは、自社の条件や制約のなかで、どこまでDX内製化するのか、どこから外部パートナーと組むのかを現実的に決めることです。そのために必要な観点を、失敗学・アンチパターンという切り口から整理していきます。
なぜ今、DX内製化で「燃え尽き」が多発しているのか
まず押さえておきたいのは、DX内製化ブームの背景そのものです。クラウドサービスやローコード/ノーコードツールの普及により、「これなら自分たちでも作れそうだ」という感覚を持ちやすくなりました。また、業務を深く理解している現場側が主導するDX内製化は、外部委託よりもスピーディに価値を出せるように見えます。その結果、「DXの内製こそが正義」「DX内製化こそがこれからのスタンダード」といった空気が生まれ、開発体制の準備や人材戦略よりも前に「とにかく内製化を進めよう」という掛け声だけが先行しがちです。
しかし、実際の現場で起きている内製化 失敗をたどると、燃え尽きの原因は技術力不足だけではないことが分かります。多くの場合、DX内製化の目的が曖昧なままプロジェクトがスタートし、「コスト削減」「スピード向上」「ノウハウ蓄積」「レガシー刷新」など、複数の目的が一度に掲げられます。その結果、現場は何を優先すべきか分からなくなり、開発体制の中での意思決定も遅れがちになります。DXの内製は、単にプログラムを自社で書くことではなく、ビジネス目標を起点とした継続的な改善プロセスです。この認識が共有されないままシステム内製化を進めると、「やることリスト」だけが増え、チームは疲弊していきます。
もう一つの要因は、DX内製化に取り組む企業側の期待値の高さです。経営層からすると、「DX内製化すれば社内に強い開発体制ができ、競争力が高まる」というイメージを抱きがちです。しかし、現場では既存業務がそのまま残っており、DXの内製にフルコミットできるメンバーは限られています。兼務状態でのDX内製化は、短期的には回っているように見えても、半年〜1年のスパンで見れば燃え尽きや品質低下を招きやすい構造です。DX内製化を本当に成功させるには、「何をやるか」だけでなく、「何をやめるか」「どの業務を削って開発体制に時間を割くか」といった痛みを伴う判断も必要になります。
Tips:DX内製化を始める前に確認したい3つの問い
1. DX内製化の目的は何か(コスト・スピード・知見・競争力のどれを優先するか) / 2. 今の開発体制で、誰がどの業務を減らせば内製の時間を捻出できるか / 3. 1〜2年は継続してDX内製化に投資する覚悟があるか。これらに答えられない場合、DXの内製は「燃え尽きプロジェクト」になりやすい状態と言えます。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
DX内製化の失敗構造:体制・設計・採用の三重苦
次に、DX内製化の内側で何が起きているのかを、構造として捉えてみます。多くの企業で共通するのは、体制・設計・採用の三つがそれぞれ不十分なまま進められ、互いに悪影響を与え合うことです。例えば、「とりあえずプロジェクトチームを作ったからDX内製化を始めよう」と走り出したものの、プロダクトオーナーや意思決定者の役割が曖昧なため、要件が揺れ続けるケースがあります。こうした開発体制では、意思決定のたびに会議が増え、メンバーは会議対応と実装作業の両方で疲弊していきます。
同時に、設計面でもアンチパターンが重なります。PoCで使ったツールや構成を、そのままDX内製化の本番基盤として流用してしまうと、運用やセキュリティ、監査対応などの非機能要件が後回しになりやすくなります。結果として、「とりあえず動くもの」はできても、少し機能追加をするたびに全体改修が必要になる「拡張不能なシステム」が生まれ、これが内製化 失敗の引き金になってしまいます。DXの内製では、技術スタックの選定以上に、「変化に耐えられる設計かどうか」「運用チームが回せるかどうか」という観点が重要です。
最後の要素が採用・育成です。DX内製化に取り組む企業ほど、「フルスタック」「DX経験者」「クラウドネイティブ」といったキャッチーな要件で求人を出しがちですが、現実には市場競争が激しく、そうした人材は簡単には採用できません。そこで、「社内で詳しそうな若手」を中心にDXの内製を進めると、特定の個人に依存した開発体制ができあがります。属人化が進んだ状態でその人材が異動・退職すると、システム内製化は一気に失速し、「やはり外注の方が安全だった」という結論に逆戻りしてしまいます。体制・設計・採用のどれか一つだけでも崩れると、DX内製化はじわじわと内側から壊れていく。その連鎖構造を理解することが、まず最初の一歩です。
体制設計のアンチパターンと、燃え尽きない開発体制の作り方
DX内製化を支える土台となるのが開発体制です。ここでよく見られる内製化 失敗のパターンは、「誰が何を決めるか」が曖昧なまま走り出すことです。例えば、「業務部門から1名」「情報システム部から1名」「現場リーダーから数名」を集めてDX内製化チームを作ったものの、最終的な仕様決定者がいないため、要件が決まったはずなのに、別の会議で再びひっくり返る…という状況が起こります。これは、RACIのような責任分解が行われておらず、「責任を持つ人(Accountable)」が不在の開発体制になっているからです。
燃え尽きない開発体制を作るには、まず役割と権限の線引きを丁寧に行う必要があります。プロダクトオーナー(事業責任者)は「何を作るか」「どの順番で価値を出すか」を決める役割を持ち、テックリードは「どのように作るか」「どのレベルの品質を担保するか」を判断します。業務部門の代表は、現場ニーズの優先順位や運用の制約条件を整理し、開発チームに橋渡しする役目です。こうした役割を明文化し、「この決定は誰が最終責任を持つのか」を開発体制のなかで合意しておくことで、意思決定のスピードと質が大きく変わります。
また、DXの内製は多くの場合、メンバーが既存業務と兼務で参加することになります。ここでのアンチパターンは、「本業はそのまま、DX内製化を追加でやってください」とお願いしてしまうことです。これでは、メンバーは常に時間に追われ、DX内製化に十分な集中時間を割けません。現実的には、プロジェクト期間中だけでも「このメンバーは業務Aの担当を減らし、DX内製化に週20時間を割く」といった具体的な時間配分を、所属長を含めて調整する必要があります。開発体制の議論は、人の「名前」だけでなく、「時間」と「優先度」まで含めて設計して初めて機能します。
さらに、ステークホルダーとのコミュニケーション設計も重要です。DX内製化の現場では、進捗報告が「機能一覧」や「実装状況」の説明に偏りがちですが、現場マネージャーや経営層が知りたいのは「どの業務がどのように良くなるのか」「開発体制は持続可能か」という点です。定例のふりかえりでは、「今スプリントで価値を出せたこと」「開発体制として無理をしているところ」「内製化 失敗の芽になりそうなリスク」を率直に共有し、必要であればスコープ縮小や優先順位変更を提案する。このような対話を継続できる組織が、DX内製化を長期戦として戦える企業です。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
PoC止まりからの脱却:運用まで見据えたDX内製化の設計思考
DX内製化の設計における代表的な内製化 失敗パターンは、PoCの延長線上で本番システムを作ってしまうことです。短期間で価値を確認するためのPoCは、「動くこと」に重きが置かれがちで、運用・保守・監査・可観測性といった非機能要件は後回しになりやすい構造です。そのままDXの内製で本番化すると、リリースはできたものの、ログが取れておらず障害調査ができない、権限管理が甘く監査で指摘される、運用マニュアルがなく問い合わせが現場に集中する、といった問題が立て続けに起こります。これが続くと、開発体制は火消し対応で手一杯となり、新しい改善に手が回らなくなります。
これを避けるためには、「最初からすべて完璧に作る」のではなく、「最初から運用を前提に設計する」ことが重要です。例えば、DX内製化の初期段階では、機能要件と同じくらいの粒度で「ログの方針」「監視の方針」「データのライフサイクル」「権限ロール」「障害発生時の一次対応フロー」といった非機能要件を定義します。これらは、後から付け足そうとしても、システム全体の構成を変えないと対応できないことが多く、システム内製化の負債として将来の開発体制を苦しめる要因になります。
また、アーキテクチャ選定でも、「今、チームにいる特定のエンジニアが得意だから」という理由だけでマイナーなフレームワークやサービスを採用すると、数年後の内製化 失敗の種になります。DX内製化は中長期の取り組みであり、メンバーの入れ替わりや組織変更は必ず起こります。将来の開発体制でも習得しやすく、社外の情報やコミュニティが十分にある技術スタックを選ぶことが、DXの内製を持続させるうえでの現実的な選択です。
補足:設計レビューで押さえたいチェック観点
DX内製化の設計レビューでは、機能仕様だけでなく、「運用担当者は誰か」「障害時の連絡フロー」「ログやメトリクスの確認方法」「データの削除・マスキング手順」など、運用プロセスを一緒に確認することをおすすめします。設計段階で運用フローまで合意できれば、開発体制と運用体制の齟齬が減り、システム内製化の負債も軽減できます。
「採れない・育たない・辞める」を避けるDX人材戦略
DX内製化を続けるためには、当然ながら人材が必要です。しかし、「DXエンジニア」「フルスタックエンジニア」といったキーワードで募集をかけても、期待どおりの人材がすぐに採用できるとは限りません。実際、多くの企業が「IT人材不足」を理由にDX内製化を断念したり、内製化 失敗を経験しています。ここでのアンチパターンは、「完璧な人を一人採ること」にこだわりすぎることです。特定のスーパーマンを採用してDXの内製を任せようとしても、その人物に依存した開発体制は、長期的には大きなリスクになります。
現実的なアプローチは、「どの役割を社内で担うか」「どこを外部パートナーに頼るか」を明確にすることです。例えば、業務理解と企画・要件整理は社内のDX推進チームが担い、アーキテクチャ設計や最初の実装は外部パートナーと協働する。DX内製化の初期フェーズでは、このように役割を分けたうえで、社内メンバーが外部の専門家からレビューや設計の考え方を学び、徐々に自走できる開発体制を整えていくのが現実的です。採用する人材も、「何でもできる人」ではなく、「業務に強いPM」「運用に強いエンジニア」「データに強いアナリスト」など、役割に応じて分担した方が、育成や評価も行いやすくなります。
育成面では、レビュー文化とドキュメント整備が鍵になります。せっかくDX内製化のために採用したエンジニアに仕事を丸投げし、コードレビューも設計レビューも十分に行わない開発体制では、スキルが属人化し、他のメンバーが成長できません。さらに、評価制度が従来の事務・営業中心のもののままだと、DXの内製で長期的な基盤整備を頑張っている人の貢献が正しく評価されず、モチベーション低下や退職につながります。DX内製化を戦略的に進めるのであれば、「技術負債の返済」「運用の安定化」「再利用可能なコンポーネントづくり」といった、長期的な価値を評価軸に組み込むことも検討したいところです。
そして何より、「人材がいないからDX内製化は無理だ」で終わらせず、現有戦力でどこまで内製化できるかを冷静に見極めることが重要です。無理に大きなスコープでDXの内製を掲げるよりも、小さな範囲から始めて成功体験を積み、徐々に開発体制とスキルを引き上げていく方が、結果として内製化 失敗のリスクは小さくなります。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
内製・外注・伴走の見極め方と、失敗からの立て直し
ここまで見てきたとおり、DX内製化には多くの落とし穴があります。しかし、「難しそうだからやめる」ではなく、「どこまでDX内製化すべきか」「どこは外注や伴走支援を活用すべきか」を見極めることで、現実的な着地点を見つけることができます。ポイントは、自社にとってのコア領域を見極めることです。顧客体験やデータ分析、業務フローの設計など、競争優位の源泉となる部分は、できるだけDXの内製で意思決定力とスピードを高める。一方で、インフラ基盤、共通機能、監査対応などは、外部パートナーの知見を借りながら進める。このようなハイブリッドな開発体制が、現場負荷を抑えつつ内製化 失敗を避けるうえで有効です。
「すでにDX内製化で燃え尽きてしまった」場合でも、立て直しは可能です。まずは、現状のプロジェクトを棚卸しし、「今、本当に必要な機能」と「後回しにできる機能」を整理します。そのうえで、スコープを一度絞り込み、開発体制の再設計に時間を割きます。必要であれば、一部の領域は外注や伴走支援を活用し、DXの内製チームは「コア機能と運用の安定化」に集中してもよいでしょう。また、既存システムの設計をレビューし、「作り直すべき部分」「ラップして延命できる部分」「廃止候補の機能」などに分類することで、システム内製化の負債を減らす道筋が見えてきます。
このプロセスで大切なのは、「DX内製化の旗を下ろすこと」ではなく、「DXの内製を続けるための現実的な形に作り替えること」です。内製・外注・伴走のバランスは、会社のフェーズや人員、予算によって変わります。開発体制を見直す対話の場には、経営層・現場マネージャー・DX推進責任者・情報システム部門を巻き込み、「何を諦め、何に集中するか」を率直に議論する必要があります。もし、「自社だけで判断するのが難しい」と感じた場合は、DX内製化や開発体制の設計に詳しいパートナー企業に第三者目線でレビューを依頼するのも一つの選択肢です。
チェックリスト:DX内製化の見直しタイミング
・半年以上、リリースしても現場の業務がほとんど変わっていない / ・DX内製化の担当者の離職や異動が続いている / ・開発体制のメンバーが「常に火消し」状態になっている / ・新しい企画よりも障害対応や問い合わせが優先されている。これらに複数当てはまる場合は、一度立ち止まり、内製・外注・伴走のバランスを再設計するサインかもしれません。
まとめ:DX内製化を「燃え尽きプロジェクト」にしないために
DX内製化は、うまくいけば自社に大きな競争力をもたらす一方で、進め方を誤ると内製化 失敗によって現場と組織に深い疲弊を残します。本記事で見てきたように、DXの内製が燃え尽きる背景には、体制・設計・採用という三つの要素が複雑に絡み合う構造があります。DX内製化を検討・推進している立場であれば、まずは「自社の開発体制は、誰が何を決めているか」「設計は運用まで見据えられているか」「人材戦略は現実的か」という問いを、自分たちにも投げかけてみてください。
大切なのは、「内製するか・しないか」という二択ではなく、「どの範囲をDX内製化し、どの範囲で外部の力を借りるか」を設計することです。コアな領域はDXの内製によって意思決定のスピードと学習サイクルを高め、非コアな領域は専門性の高い外部パートナーに委ねる。そうすることで、開発体制に無理な負荷をかけず、継続的に価値を生み出すDX内製化が実現しやすくなります。もし、今進めているDX内製化が「燃え尽きプロジェクト」になりつつあると感じたら、一度立ち止まり、体制・設計・採用の三つの観点から現状を棚卸ししてみてください。
そのうえで、「自社だけで抱え込まない」視点も大切です。内製・外注・伴走のバランスを見直す過程で、第三者の視点や他社事例を取り入れると、「ここまではDX内製化で頑張る」「ここから先はパートナーと一緒に進める」といった現実的な選択肢が見えてきます。本記事が、DXの内製に携わる皆さまにとって、少しでも視野を広げ、次の一歩を考えるきっかけになれば幸いです。
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い





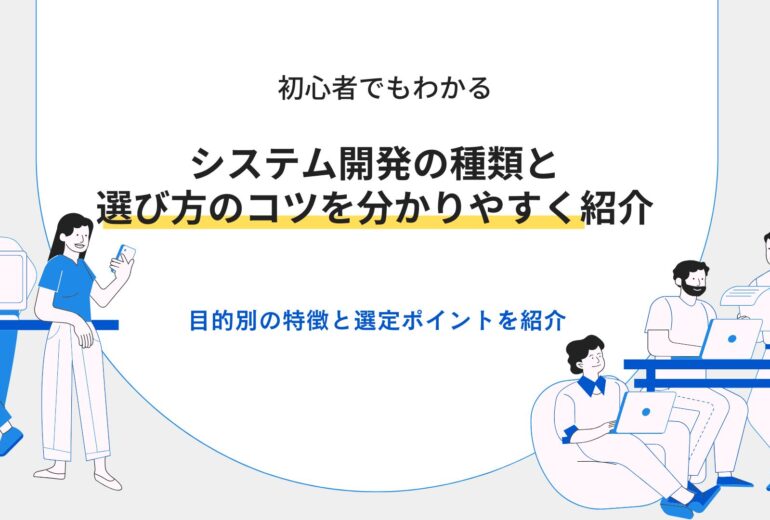










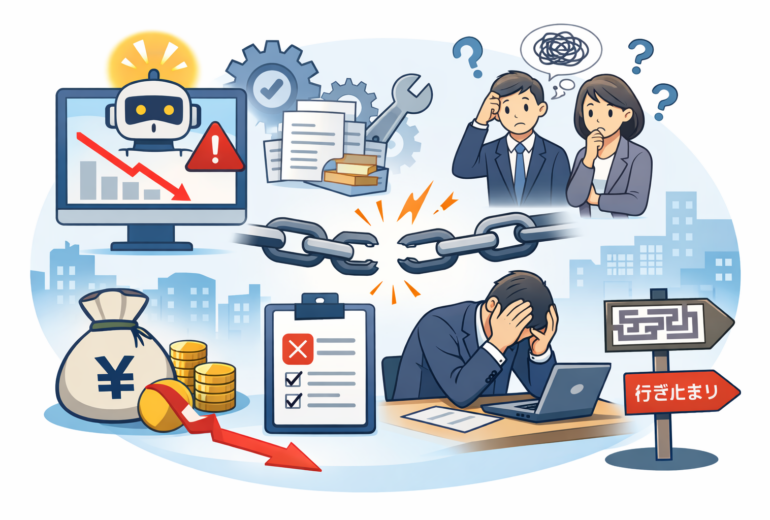


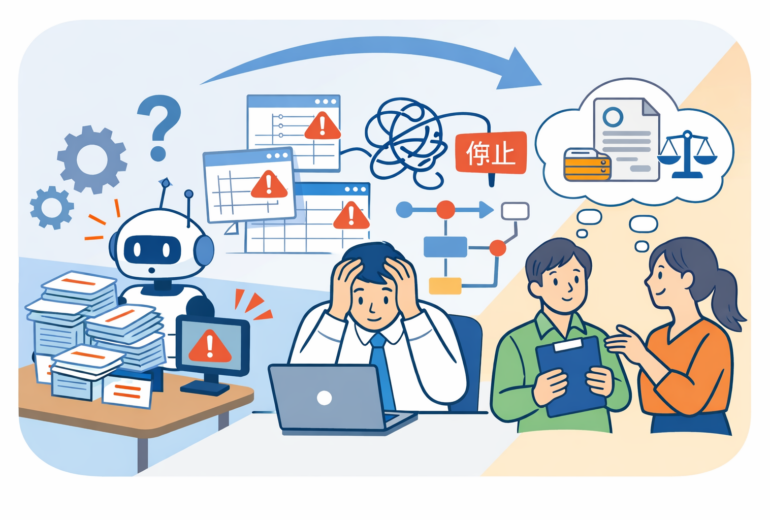



コメント