Contents
ユーザー教育の仕組み化で、CSと情シスの「説明地獄」から抜け出す
カスタマーサクセス担当や情報システム部の方なら、「マニュアルもFAQもあるのに、結局みんな人に聞きに来る」「新しいシステムを導入するたびに説明会と問い合わせ対応でヘトヘトになる」という経験があるのではないでしょうか。こうした状況の背景には、コンテンツの量や質だけではなく、ユーザー教育が“仕組み”として設計されていないことがあります。言い換えると、ユーザーオンボーディングが「一度説明して終わり」のイベント型に留まり、日々の利用に寄り添う継続プロセスになっていないのです。
本記事では、オンボーディングメールとチュートリアルを軸に、ユーザー教育をどう仕組み化すべきかをCSと情シスの両方の視点から整理します。登録直後から初回価値体験、そして利用定着までの流れを、具体的なメール設計やインアプリのチュートリアル設計と結びつけて解説し、最後に「今日から何をすればいいか」が分かる実装ステップまで落とし込みます。現場でそのまま使える考え方とテンプレートの土台として、自社のユーザー教育設計に役立ててください。

1. なぜ今「ユーザー教育の仕組み化」が必要なのか
まず押さえたいのは、なぜここまでユーザー教育が重要になっているのかという背景です。SaaSやクラウドサービスが当たり前になり、社内でもツールが増え続ける中で、「一度説明会を開いて終わり」では追いつかない状態が常態化しました。CSの現場では、せっかくマーケティングが獲得したリードがトライアルのまま離脱したり、導入まで進んでも価値を十分に引き出せずチャーンしてしまうケースが課題になります。情シスの現場では、新システム導入のたびに説明会と個別問い合わせが集中し、本来優先したいセキュリティ対策や基盤整備に手が回らない事態が起こりがちです。
ここで重要なのは、ユーザーは「説明を聞きたい」のではなく、「自分でできるようになりたい」ということです。ユーザー教育が機能していないと、社外ユーザーはチャットサポートやメールに頼り続け、社内ユーザーは情シスや詳しい同僚に同じ質問を繰り返します。その結果、CSや情シスは問い合わせ対応に追われ、改善施策や価値提案に時間を使えません。逆に、オンボーディングメールとチュートリアルを組み合わせて、ユーザーオンボーディングを“プロセス”として設計できると、ユーザーが自然と「次に何をすればよいか」を理解し、自走状態に近づいていきます。
ユーザー教育の仕組み化とは、「誰に・いつ・どのチャネルで・何を伝えるか」を明文化し、それをツールとコンテンツで再現可能にすることです。中心となるチャネルが、登録直後や導入直後に届くオンボーディングメールと、画面上で操作を導くチュートリアルです。この二つを丁寧に設計することで、説明会や個別対応に依存しないユーザー教育が可能になり、CSと情シスの負荷も着実に下げられます。
ポイント:ユーザー教育を「コンテンツを作ること」だけに限定せず、ユーザーオンボーディングというプロセスをどう設計するかに視点を移すことが出発点です。その中心にあるのが、オンボーディングメールとチュートリアルです。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
2. オンボーディング全体設計:メールとチュートリアルの役割分担
次に、ユーザー教育を仕組み化するうえで欠かせないのが、ユーザージャーニー全体の設計です。多くのプロダクトや社内システムでは、「登録直後(またはアカウント発行直後)」「初回ログイン」「初回価値体験(最初の成功体験)」「習慣化・定着」というフェーズが存在します。各フェーズで、オンボーディングメールとチュートリアルの“役割”を分けると、全体像が一気に見えやすくなります。
たとえば「登録直後〜初回ログイン」までは、ユーザーの主な接点はメールです。この段階では、ウェルカムメッセージとともに、「アカウント有効化」「初回ログインURL」「最初の1アクション」をメールで明確に伝えます。ここで機能一覧を長々と説明するのではなく、「30秒でできること」を具体的に示し、最初のハードルを下げるのがポイントです。その後「初回ログイン〜初回価値体験」までは、画面上で操作を支援するチュートリアルが主役になります。チェックリスト形式やツールチップで「ここをクリックしてテンプレートを作成」「最初の案件を登録」など、迷いを起こしやすい箇所を操作体験の中で解消していきます。
さらに「初回価値体験〜習慣化」に移ると、再びメールが効いてきます。このフェーズでは、活用事例やベストプラクティス、よく使われる機能の紹介を通じて、ユーザー教育の対象を「基本操作」から「うまく使いこなす方法」へシフトさせます。ここで重要なのは、メールの内容を一律にしないことです。たとえば「まだ初期設定が終わっていないユーザー」「基本操作はできているが高度な機能は使っていないユーザー」など、ステータスに応じてメールやチュートリアルを出し分けると、押しつけ感を減らしつつ効果を上げられます。
社内システムでも考え方は同じです。情シスが新ツールを導入する際、最初のオンボーディングメールで「目的」「主要メリット」「最初に覚えるべき3操作」を端的に伝え、ログイン後は画面内のチュートリアルで実際の操作をガイドします。そして運用が落ち着いてきたタイミングで、「申請の裏側で何が変わったのか」「生産性にどんな効果が出ているか」を共有する教育メールを追加すると、現場の納得感と定着度を高められます。
ユーザー教育の全体設計では、マーケ・プロダクト・CS・情シスがバラバラにコンテンツを作るのではなく、「どのフェーズの教育を、どのチームが担当するか」を決めておくことも重要です。これにより、メールとチュートリアルが重複したり、逆に抜け落ちたりするリスクを減らせます。
3. 実務で使えるオンボーディングメール設計のポイント
ここからは、オンボーディングメールを実務でどう設計するかを詳しく見ていきます。多くの企業がやりがちなのは、「ウェルカムメールを1通だけ送り、その後のユーザー教育は個別フォローで何とかする」というパターンです。しかし、ユーザーオンボーディングを仕組みとして考えるなら、3〜5通を“シリーズ”として設計するのがおすすめです。
たとえばSaaSや外部ユーザー向けプロダクトなら、以下の流れが典型です。1通目はウェルカムと初回ログイン案内に絞り、「最初のセットアップ」を短く提示します。2通目では簡単なチュートリアル動画やステップガイドを紹介し、「初めての○○を登録してみましょう」と具体的な行動を促します。3通目では活用事例やよくある質問へのリンクを通じて、「うまく使うコツ」を共有します。4通目以降は未利用機能へのナッジや、プランに応じた高度機能の紹介など、“使いこなし”のユーザー教育へ移行するとよいでしょう。
オンボーディングメールは単なるお知らせではなく、「次の一歩」を迷わせないための設計が大切です。そのためには、件名・冒頭の1文・CTAボタンの3つを特に意識します。件名では「【3分で完了】初回設定のご案内」のように、行動量と価値を具体的に伝えます。冒頭では「このメールのゴールは〇〇です」と目的を明確にし、CTAボタンには「テンプレートを作成する」「最初の案件を登録する」など、具体的な動詞を使います。社内向けなら「この手順に沿って設定すると、XX部門の申請が今日からスムーズになります」といった、現場メリットを短く添えると効果的です。
また、メールの中にはチュートリアルやヘルプ記事へのリンクを積極的に埋め込みます。たとえば「詳しい手順はチュートリアル動画へ」「画面キャプチャ付きガイドはこちら」のように、ユーザー教育の導線をメール内で完結させます。このときリンク先の整理も重要です。「/onboarding-mail/tutorial」「/user-education/getting-started」など、誰が見ても分かる導線にしておくと、CSや情シス側で運用しやすくなります。
現場でよくある落とし穴
・オンボーディングメールの頻度が高すぎて開封されなくなる
・営業色が強すぎて「売り込みメール」と認識されてしまう
・チュートリアルやヘルプへのリンクが散らばり、どこを見ればよいか分からない
対策:「1通1ゴール」を徹底し、ユーザー教育に必要な導線だけに絞ることが効きます。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
4. チュートリアルとインアプリガイドで“迷わない体験”をつくる
ユーザー教育のもう一つの柱が、プロダクト内で動くチュートリアルやインアプリガイドです。画面上のポップアップ、ツールチップ、チェックリスト、進捗バーなどを組み合わせることで、オンボーディング初期に「今どこまで進めたか」「あと何をすればよいか」を直感的に理解してもらえます。特にCSの立場では、問い合わせが多い操作をチュートリアル化することで、問い合わせ件数を直接減らす効果が期待できます。
実務的には、まず「初回価値体験」を定義することから始めます。プロジェクト管理ツールなら「最初のプロジェクトとタスクを作成し、1件担当をアサインする」、ワークフローシステムなら「1件申請を出して承認が完了する」など、ユーザーが「役に立つ」と実感できる最低限の状態です。次に、その状態に到達するまでのステップを3〜5個程度に分解し、チュートリアルとして実装します。チェックリストで「1. プロジェクトを作成する」「2. タスクを追加する」「3. メンバーを招待する」と表示し、達成した項目にチェックが入るようにすると、前進している感覚が伝わりやすくなります。
インアプリガイドでは、「コンテキスト」と「タイミング」が成否を左右します。ユーザーが初めてボタンをクリックしたときだけツールチップを出す、初回ログイン時だけ案内バーを表示する、などのルールを設けることで、必要なときにだけガイドが出る状態を作れます。また、使いこなしているユーザーにとってはガイドが邪魔になりやすいので、「スキップ」「次回から表示しない」は必須です。社内システムなら、権限やセキュリティなどミスが許されない画面にだけ詳細なガイドを出す、といった使い分けも有効です。
こうしたインアプリのチュートリアルとオンボーディングメールは、セットで設計されるべきです。たとえば2通目のメールで「最初の申請を出してみましょう」と案内し、リンク先の画面で「初めてこの画面に来たユーザーだけに表示されるチュートリアル」を出す、という構成です。これにより、メールで投げっぱなしにせず、画面上でユーザー教育を完結させられます。

5. 自動化・改善サイクルと、今日から始める実装ステップ
最後に、ユーザー教育を継続的に改善していく観点と、CS・情シスが今日から動き出すためのステップを整理します。重要なのは、「作って終わり」にしないことです。オンボーディングメールなら、開封率・クリック率だけでなく、その後の行動(初回ログイン、初期設定完了、初回価値体験達成)まで追って、オンボーディングへの貢献度を評価します。チュートリアルなら、開始率・完了率・各ステップの離脱率を追い、どのガイドがユーザー教育として効いているかを数字で確認します。
KPIの例としては、「登録から初回価値体験までの平均日数」「オンボーディング期間中の問い合わせ件数」「社内システム導入後1か月のヘルプデスク工数」「特定機能の利用率」などが挙げられます。これらを定点でウォッチしながら、件名や配信タイミング、チュートリアルのステップ数や文言を小さく変えてテストします。A/Bテストまでできなくても、「今月は初期設定メールにチュートリアル動画を追加」「来月はチュートリアルのステップを3つに絞る」といったように、1か月1改善でも十分効果が出ます。
具体的な始め方としては、次の三段階が現実的です。ステップ1:CSと情シスが協力して、「問い合わせが多い上位3テーマ」を洗い出します。ステップ2:その3テーマに対応するオンボーディングメールと簡単なチュートリアル(静止画+テキストでも可)を作り、1〜2か月ほど試験運用します。ステップ3:効果を見ながら、ユーザージャーニー全体のオンボーディング設計へ広げていきます。最初から完璧なフローを作ろうとするより、小さく始めて回しながら育てる方が、現場負荷も小さく定着しやすいのが実情です。
株式会社ソフィエイトは、こうしたユーザー教育の仕組み化を外部パートナーとして支援できます。具体的には、オンボーディング設計ワークショップ、オンボーディングメールのテンプレートや配信フロー設計、画面構成を踏まえたチュートリアル設計、ヘルプセンターやナレッジベースとの連携設計などです。CSと情シスだけでは手が回らない部分を補いながら、自社に合ったユーザー教育の仕組みを一緒に作り上げることで、「説明に追われる組織」から「ユーザーが自走し、チームが価値創出に専念できる組織」への転換を目指せます。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
まとめ
本記事では、CSと情シスの現場で起こりがちな「説明会と問い合わせ対応に追われる状態」から抜け出すために、ユーザー教育をどう仕組み化すればよいのかを解説しました。ポイントは、ユーザーオンボーディングを“プロセス”として捉えること、そしてその中心にオンボーディングメールとチュートリアルを置くことです。登録直後から初回価値体験、そして利用定着までの各フェーズで役割を整理し、ユーザーが「次に何をすればよいか」を迷わず理解できる状態をつくることが、問い合わせ削減と定着率向上の両方につながります。
また、ユーザー教育は一度作って終わりではなく、データを見ながら改善を続けるサイクルです。メールの開封・クリック・行動データ、チュートリアルの開始・完了・離脱データを眺めながら、「問い合わせの多いテーマから優先的に改善する」といった小さな一歩を積み重ねることが重要です。その過程で、社内だけでは設計・実装が難しい部分については、外部パートナーの力を借りることも選択肢の一つです。
ユーザー教育の仕組みが整えば、CSはより高度な価値提案やアップセルに、情シスはより戦略的なIT投資やセキュリティに時間を使えるようになります。ぜひ、自社のオンボーディングメールとチュートリアルを「自走するユーザー」を生み出す仕組みとして見直し、現場の負荷軽減とユーザー価値の最大化を同時に実現していきましょう。
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発:スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング:業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webの体験設計とUI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い










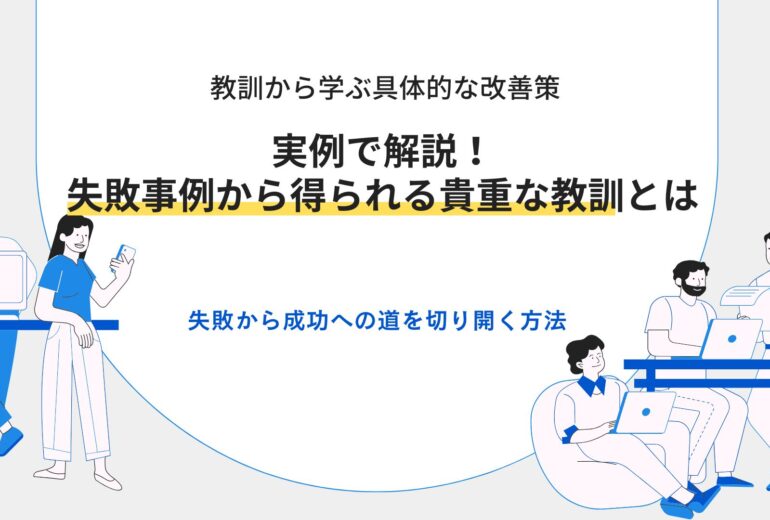












コメント