Contents
営業が「記憶」に頼る危うさとは?
BtoB営業において、担当者の「記憶」に頼った顧客対応は多くのリスクをはらんでいます。営業担当者は多数の顧客やタスクを抱え、次回のアプローチ日や商談内容など覚えておくべき情報が膨大です。しかし人間の記憶には限界があり、うっかり連絡や約束を忘れてしまうことも少なくありません。
たとえば「後でメールする」と思いつつ失念すれば、顧客に「放置された」と感じさせ信用を損ねる恐れがあります。実際、たった一度の連絡漏れが原因で取引終了に至るケースもあり、こうしたミスの積み重ねは機会損失に直結します。さらに「いつも対応が遅れる」「言ったことを忘れる」といった評判が立てば、企業全体の信用低下にもつながりかねません。
また、「記憶頼み」の営業は情報が担当者個人に属人化しやすい問題も孕んでいます。顧客とのやりとりの履歴が担当者の頭の中や手元のメモだけに留まっていると、担当者が不在の際に代わりの対応ができず商談が止まってしまったり、引き継ぎ時に齟齬が生じたりします。情報が社内で共有されないまま放置されれば、「○○の案件はあの人しか状況を知らない」といった属人的な運用になりがちです。その状態が続くと再現性や安定性を欠いた危うい組織になってしまいます。
営業の記憶依存がもたらす3つのリスク
- 連絡漏れ・約束忘れ:顧客の信頼を損ない、機会損失につながる
- 情報の属人化:担当者不在時の対応困難、引き継ぎ時の齟齬
- 組織の不安定性:エース社員の異動・退職で業績が急落するリスク
つまりエース社員の個人技に頼る体制では、本人が異動・退職した途端に業績が立ち行かなくなるリスクが高いのです。「記憶に頼る営業」から脱却しない限り、こうした不安定さは常につきまといます。
営業DXの第一歩は「やりとりの可視化」から
では、営業組織の安定性と生産性を高めるには何から始めればよいでしょうか。デジタルトランスフォーメーション(DX)による営業改革の第一歩は、顧客との「やりとりの可視化」です。可視化とは、これまで担当者個人の頭や各自のメールボックス・ノートに散在していた取引先との会話や約束事を、チーム全員が見られる形で「見える化」することです。
具体的には、商談メモやメール履歴、電話の記録など顧客との接点情報を一元管理し共有することを指します。情報が社内のあちこちに点在している状態を改め、まずは「誰でも迷わず必要な情報にたどり着ける」仕組みを作ることが肝心です。
たとえば顧客ごとに共有フォルダやシートを一つ設けて対応履歴を記録したり、名刺管理や顧客管理ツール(CRM)を導入して連絡先や商談メモを集約するなど、小さな工夫から始められます。そうすることで、「記録する=チームを助ける」という意識も生まれ、営業情報が組織の財産として蓄積されていきます。
情報の可視化が進めば、営業担当者だけでなくマネージャーや他部署も含め組織全体で顧客対応の状況を把握できるようになります。たとえば、ある取引先に対し「いつ誰が何回メールを送り、どんな電話をして、最近どんな商談をしたか」といった接点履歴が一目で分かれば、担当者が不在でも代わりに即座にフォロー可能です。
近年では、Sansanのようなサービスが名刺交換やメール、電話、面会など顧客とのあらゆる接点情報を自動蓄積し、組織全体で共有・可視化する機能を提供し始めています。こうした仕組みにより、「自社と取引先の関係性を誰もが把握できる状態」を作り出せれば、属人的な営業から脱却してチーム全体で戦略的なアプローチを検討することも可能になります。
営業情報の可視化で実現できること
- 過去の商談内容や約束事の即座な確認
- 担当者不在時の代替対応の円滑化
- 新入社員や異動者のキャッチアップ時間短縮
- 顧客対応の品質向上と標準化
- 営業活動の分析・改善サイクルの加速
まずは日々のやりとりを記録・共有する文化を根付かせること──これが営業DXへの確かな第一歩となるのです。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
AIで営業のやりとりを「自動で」整理・記憶するには?
情報可視化の重要性を押さえたら、次はそのプロセス自体を効率化・高度化する段階です。従来、営業担当者は商談後にノートやSFA/CRMへ手入力で記録を残す必要がありました。しかし近年のAI技術を活用すれば、こうした「記録する」作業を自動化し、人間の記憶に頼らずとも常に正確な営業データを蓄積できるようになります。
具体的な例として、電話やオンライン商談の内容を自動で記録・要約してくれるAIツールがあります。日本発のサービス「pickupon(ピクポン)」は、「電話&MTG議事録AI」として、通話や会議の内容をAIがリアルタイムに聞き取り文字起こしし、重要な発言をピックアップして営業支援システム(SFA)やCRMに自動で入力してくれるのが特長です。
これにより営業担当者が後から長い時間を割いて記録を書く必要がなくなるだけでなく、顧客とのやりとりがテキストと音声という形で一次情報として残るため、商談内容のブラックボックス化や属人化といった問題も解決できます。つまり会話の生データが組織の財産となり、「誰かの頭の中だけにある情報」が減っていくのです。
加えて、重要なキーワード(例えば顧客の課題や要望)をAIが自動抽出し、社内チャットでチーム共有する、といった機能も備えており、メンバー全員で顧客理解を深めることができます。
また、音声解析AIを搭載した通話支援ツール「MiiTel(ミーテル)」のように、営業の電話・Web会議・対面商談などあらゆるコミュニケーションを録音・文字起こしし、解析してくれるツールも登場しています。MiiTelでは通話が自動でテキスト化されるだけでなく、話す速度や声の抑揚、相槌の頻度といった要素が数値化されフィードバックされます。
これにより、「早口すぎないか」「相手の反応にしっかり共感できているか」など営業トークの改善点が可視化され、AIがコーチのように具体的なアドバイスを提示してくれます。このようにAIを活用すれば、商談記録の自動化による「記憶の外部化」だけでなく、会話内容の質的な分析まで含めて営業活動をサポートできるのです。
AI営業支援ツールの主な機能
- 自動文字起こし:通話・会議の内容をリアルタイムでテキスト化
- 重要ポイント抽出:顧客の課題・要望・キーワードを自動でピックアップ
- CRM連携:SFAや顧客管理システムへの自動データ入力
- 営業分析:話し方・相槌・声のトーンなどの数値化・改善提案
- チーム共有:商談内容の自動要約と社内共有
結果として、営業担当者は記憶違いや記録漏れを心配することなく目の前の商談に集中でき、後から振り返りや共有も容易になります。AIがまさに「営業チーム全体の記憶装置」として機能することで、「記憶に頼らない営業」の実現に大きく近づくでしょう。
【事例】記録×AIで「誰でも成果が出せる営業組織」に変革した中小企業
実際に、取引先とのやりとりを記録・共有する仕組みとAIを活用することで、属人性を排しチーム全員が成果を出せる営業組織へと変革した中小企業の例があります。しろくま電力株式会社(再生可能エネルギー発電の開発・電力小売を手がける2016年設立のベンチャー企業)は、その好例です。
同社では従来、テレマーケティングを含むインサイドセールスの現場で、電話営業の内容を各担当者が手作業で記録していました。リード情報の可視化やマーケ部門から営業部門へのスムーズな引き継ぎが課題となる中、2023年に通話議事録AI「pickupon」を導入。CRMとして使用していたHubSpotと連携させ、架電内容の自動記録・共有体制を整えました。
導入後、営業電話の内容はすべてAIによって自動テキスト化され、要約がHubSpot上の顧客記録に即座に登録されるようになりました。通話後に担当者が逐一メモを起こす必要がなくなり、通話記録のURLをチームで共有して上長が即フィードバックするなど、会話内容の共有も簡単に行えるようになりました。
その結果、チーム全体のモチベーションが上がり1時間あたりの架電件数が従来より60%も増加する大きな効果が出ています。さらに、顧客とのやりとりデータが自動で蓄積され誰でも閲覧できる状態になったことで、これまで課題だったCRMへの入力漏れや商談内容のブラックボックス化・属人化の問題も解消されました。
属人的な「勘と経験」に頼る部分が減り、数字に基づいた再現性のある営業へ近づいたのです。情報が蓄積され可視化されたことで、しろくま電力では新人を含むどの営業担当者でも過去の顧客対応履歴やナレッジに容易にアクセスできるようになりました。
ベテラン社員の頭の中にだけあった暗黙知がデータ化されたことで、「誰が担当しても同じクオリティの対応ができる」組織へと変わりつつあります。実際、商談の振り返りミーティングではAIが収集したKPIデータ(架電件数やアポ獲得率、効果的なトーク例など)をもとに全員で改善策を議論できるようになり、属人性のない強いチーム作りに寄与しています。
しろくま電力の導入効果
- 架電件数:1時間あたり60%増加
- 記録作業:手入力から自動化へ
- 情報共有:チーム全体での即座なフィードバック
- 属人化解消:誰でも過去の対応履歴にアクセス可能
- 営業分析:データベース型の評価・改善サイクル
このように記録とAIの力を活用すれば、中小企業であっても「営業=属人芸」という従来のイメージを覆し、経験に左右されず誰もが安定して成果を出せる営業組織を実現できるのです。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
導入のポイントとコスト感:中小企業でも無理なく始められる
最新のAIツール活用と聞くと、「自社に導入するのは難しいのでは?」「費用が高そうだ」と構えてしまう中小企業経営者の方もいるかもしれません。しかし近年はクラウドサービスの普及により、比較的低コストかつスモールスタートで試せるソリューションが増えています。ポイントを押さえれば、中小企業でも無理なく「記憶に頼らない営業」への一歩を踏み出せるでしょう。
まず大切なのは、導入の目的を明確にすることです。ただ何となくAIを導入しても、現場が振り回されて期待した効果が得られない恐れがあります。自社の営業プロセスのどこに課題があるのか、何を改善したいのかを具体的に洗い出し、数値目標に落とし込んでおきましょう。
「見込み顧客への架電数を○割増やしたい」「提案書作成にかかる時間を半減したい」「商談から成約までのリードタイムを1ヶ月短縮したい」といった具合に、指標とゴールを定めておくのです。例えば前述のしろくま電力のケースでは、「リード情報の可視化」と「マーケ部門から営業部門への引き継ぎ円滑化」が目的でした。
このように目的が明確になれば、数あるツールの中から自社に最適なもの(例えば通話記録が強みのツールか、提案書作成支援が得意なツールか)を選びやすくなりますし、導入後の成果検証もしやすくなります。
次にコストとスモールスタートの観点です。幸い、多くの営業支援AIツールはサブスクリプション型(定額課金)のクラウドサービスとして提供されており、高価な専用機器を買ったり大規模開発をしたりせずとも利用できます。サービスにもよりますが、初期導入費用が無料で、1ユーザーあたり月額数千円程度から利用できるものがほとんどです。
例えば前述の「pickupon」は初期費用ゼロ・月額6,000円(+通話料)で始められるプランが提供されていますし、音声解析の「MiiTel」も1ユーザー月額5,980円程度から利用可能です。自社の規模や予算に応じて、まずは少人数のチームや特定の業務プロセスで試験導入し、効果を見ながら段階的に範囲を広げていくとよいでしょう。
多くのクラウドサービスは短期間のトライアル利用も可能ですので、「試してから本格導入」のハードルも低くなっています。導入にあたって忘れてはならないのが、既存環境との連携とセキュリティ対策です。せっかく良いツールを導入しても、既存の顧客台帳やメールシステムと連携できなければ手入力の手間が残ってしまい、現場に定着しません。
事前に、選定ツールが自社の使っているCRMやグループウェアとスムーズに連携できるか確認しましょう。また、顧客情報や商談内容といった機密データを預ける以上、サービス提供元のセキュリティ水準も要チェックです。具体的には、通信や保存データの暗号化、アクセス権限の管理、二要素認証の有無などを確認し、自社の情報セキュリティポリシーに適合しているか検討してください。
中小企業向けAI営業ツール導入のポイント
- 目的の明確化:具体的な課題と数値目標を設定
- スモールスタート:少人数チームでの試験導入から開始
- コスト感:月額数千円程度から利用可能なクラウドサービス
- 既存環境との連携:CRMやグループウェアとの互換性確認
- セキュリティ対策:データ暗号化・アクセス権限管理の確認
クラウドサービスではデータの保管場所(国内か海外か)や障害・情報漏洩時の対応フローも重要なポイントです。これらを確認しIT部門とも協議のうえで導入すれば、中小企業であっても安心して最新のAI営業ツールを活用できます。
まとめ:営業を「属人芸」から「仕組み」へ変えるために
「記憶に頼らない営業」への取り組みは、言い換えれば営業を個人の勘や経験による属人芸から、再現性のある仕組みへと変革することです。属人的な営業では、特定のエースに業績が偏りがちで、個人の退職・異動時に大きな損失が出ます。一方、仕組み化された営業では情報とノウハウが組織に蓄積・共有されているため、誰か一人が抜けても業務が回り、安定的に成果を上げ続けることができます。
今回見てきたように、その実現にはまず日々の顧客とのやりとりを記録し可視化すること、そして可能な範囲でAIを活用して記録・分析・共有を自動化することが効果的です。情報が整備されチーム内で「見える化」されれば、「あの案件は誰に聞けば分かる?」ではなくシステムを開けば一目瞭然という状態になり、現場の安心感も高まります。
実践のポイントは、段階的に進めることです。一朝一夕で全てをデジタル化・AI化する必要はありません。まずはメモやExcelで構わないので「営業日誌」をチームで付ける習慣をつける、重要な会話はその場でメールなど文章に残す、といった記録文化の醸成から始めましょう。
それに慣れてきたら、無料または低コストで使えるツールを導入して記録の自動化・集約に挑戦します。例えば名刺管理アプリや簡易CRMで顧客情報を一元管理したり、会議録音アプリで商談を録音してテキスト化するなど、小さなDXを積み重ねていくのです。そうした取り組みの延長線上で、本格的なAI支援ツールを導入すればスムーズに定着しやすくなります。
最後に改めて強調したいのは、営業情報は「記憶」より「記録」という考え方です。人の記憶は曖昧で消えゆくものですが、記録されたデータは財産として残り続け、分析や活用ができます。情報がしっかり記録・共有されていれば、たとえ新人や別部署の人であっても蓄積された知見をもとに顧客対応ができるため、「誰がやっても同じ対応ができる」強い営業チームを築けます。
属人芸に頼らない仕組み型の営業への転換は、中小企業のこれからの成長において避けて通れない鍵と言えるでしょう。営業DXの第一歩から一つひとつ実務に落とし込み、組織全体の力で持続的に成果を出せる営業体制をぜひ実現していただきたいと思います。
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い








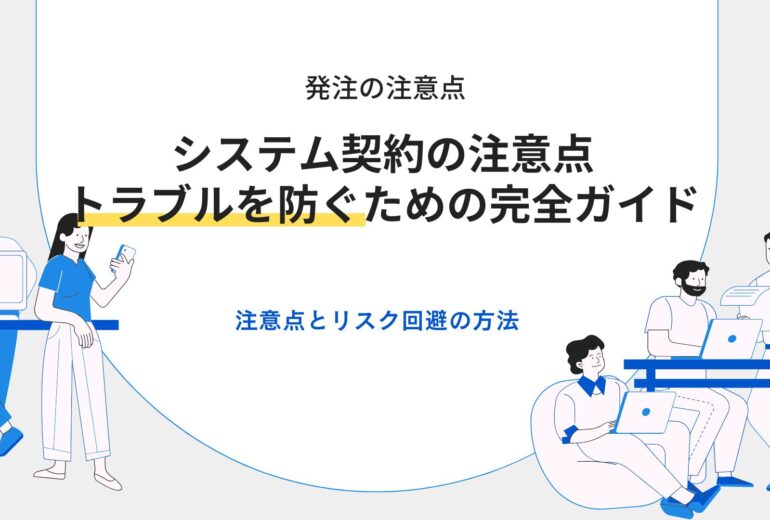








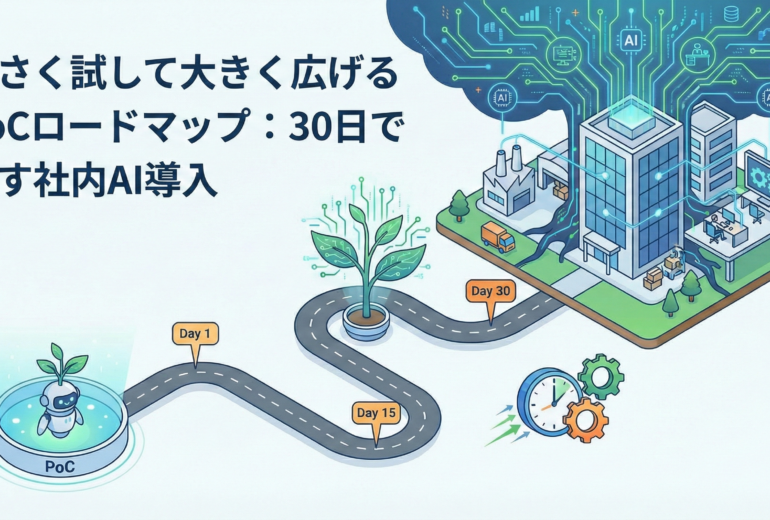






コメント