Contents
失敗学・アンチパターン:プロダクトが「機能の墓場」になる前に決めておきたい機能削減の基準
DXやAIのプロジェクトが進むほど、「なぜこんなに機能が多いのに、誰も使いこなせていないのか?」という違和感が大きくなっていきます。画面数は増え、ボタンもメニューもタブも増えているのに、現場からは「結局エクセルに戻している」「一部の機能しか触っていない」という声が聞こえてくる。この状態こそ、プロダクトが「機能の墓場」になっているサインです。
「機能の墓場」は、一気に生まれるものではありません。日々の改善会議や要件定義の場で、少しずつフィーチャークリープ(機能追加が止まらなくなる現象)が進行し、誰も止められないまま、気がつけば機能削減のハードルが極端に高くなってしまいます。特にDX・AI案件では、「せっかく投資したのだから」「この機能を入れると説得力がある」といった期待も相まって、機能が増えすぎてしまいがちです。
本記事では、こうした「機能の墓場」を失敗学の観点から整理し、フィーチャークリープを制御しながら、実務で使えるレベルの機能削減の基準をどのように設計すべきかを解説します。対象は、AI/DX導入を検討・経験している事業会社のDX推進責任者、情報システム部門、現場マネージャーの方々です。直接的なツールやサービスの宣伝ではなく、「どこまで機能を増やし、どこから機能削減と棚卸しを行うべきか」という判断軸を持ち帰っていただくことを目的としています。
この記事で扱う3つのキーワード
本文では意図的に、「機能の墓場」・「フィーチャークリープ」・「機能削減」という3つの言葉を繰り返し使います。現場の会話や社内資料の中でも、この3つを共通言語として使えるようになると、「なぜ機能が増えすぎたのか」「いつ機能削減を検討するのか」をチームで議論しやすくなります。
なぜDX・AIプロダクトは「機能の墓場」になってしまうのか
まず押さえておきたいのは、「機能の墓場」は怠慢や能力不足だけではなく、構造的な要因から生まれているということです。DX・AIプロジェクトでは、多くの場合「現場の要望を聞くべき」「営業が約束した機能に応えたい」「経営層の期待に応えたい」という善意からフィーチャークリープが始まります。1つ1つの要望はもっともらしく見え、「この機能削減はできない」「これも将来役に立つかもしれない」と後回しにされます。
しかし、機能が増えるたびに、学習コストや説明コストは確実に積み上がります。マニュアルのページは増え、オンボーディングの時間は延び、テスト観点も膨らみます。AI機能であれば、データの準備・評価・監査といった運用の負荷も増えます。つまり、「機能を増やすこと」と「価値を増やすこと」は決してイコールではなく、むしろ機能の墓場に近づくカーブを描くタイミングがあります。
さらに、DX・AIの文脈では「PoCで試した仮機能」が、本番リリース時に機能削減されないまま残りがちです。検証目的だったダッシュボードや実験的なAIの自動判定機能が、「一度作ったから」「説明資料に載せてしまったから」という理由で、プロダクトの中に居座り続けます。その結果、本当に使ってほしいコア機能が埋もれ、プロダクト全体が機能の墓場のような印象を与えてしまうのです。
こうした背景を踏まえると、「なぜ機能の墓場になったのか?」という問いは、「いつ、どのタイミングでフィーチャークリープを止め、機能削減の視点を持ち込むべきだったのか?」という問いに言い換えられます。機能の墓場を防ぐには、後ろ向きの「リストラ」としてではなく、プロダクトのライフサイクルの一部として機能削減を位置づけることが前提になります。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
機能の墓場を生むフィーチャークリープと典型アンチパターン
次に、具体的にどのようなフィーチャークリープのパターンが機能の墓場を生んでいるのかを整理します。DX・AI案件でよく見られるアンチパターンは、大きく3つの流れに分けられます。
1つ目は、「声の大きい人の要望」優先によるフィーチャークリープです。大口顧客、社内の役員、影響力の強い現場リーダーが「この機能がないと困る」と言えば、プロダクトの方向性よりもその声が優先されてしまいます。本当は例外的なユースケースであるにもかかわらず、機能削減されないまま標準機能として実装され、他の利用者にとっては不要な設定項目や操作が増えていきます。こうして少しずつ機能の墓場が形成されていきます。
2つ目は、例外対応をすべて「機能」で解決しようとするパターンです。本来であれば業務フローや運用ルールで吸収すべき例外を、安易に「ボタンを追加する」「設定項目を増やす」ことで解決しようとすると、条件分岐だらけの画面が出来上がります。フィーチャークリープが進むほど、誰も全体像を把握できなくなり、「どの機能を削ってもどこかに影響しそう」という心理が強まり、機能削減の意思決定がますます難しくなります。
3つ目は、KPIや評価指標が「機能数」や「要望対応件数」になっているケースです。本来は「業務時間を何%減らせたか」「エラー率をどれだけ下げられたか」といった成果を追うべきところが、「何画面リリースしたか」「何件の要望に対応したか」が評価されてしまうと、フィーチャークリープはむしろ奨励されることになります。結果として、現場の生産性ではなく、プロダクトの複雑性のほうが順調に成長してしまい、機能の墓場が日に日に大きくなっていきます。
AI機能に絞って見ても、似たようなアンチパターンがあります。「せっかくAIを入れるのだから、自動判定・自動分類・自動レコメンドなどを一通り揃えたい」と考え、PoCの成果をそのまま本番に持ち込むケースです。本来であれば、精度や説明可能性、データ品質を踏まえて一度機能削減を検討すべきなのに、「せっかく作ったから捨てにくい」というサンクコストの心理が働きます。その結果、「AIボタンはあるが誰も押していない」という典型的な機能の墓場が生まれます。
「この1年で追加した新機能のうち、利用率が低いものを上位10個出してみる」「仕様書やチケットを追いかけ、誰の要望から始まったのかを確認してみる」と、フィーチャークリープがどこから始まっているかが見えてきます。ここから先は、これらをどう機能削減につなげるかがポイントです。
組織の心理的ブロックを越えて機能削減を「普通の仕事」にする
ここまで読むと、「うちも機能の墓場になっている気がする」「フィーチャークリープを止めたい」と感じる方も多いと思います。しかし、頭では分かっていても、実際に機能削減に踏み出すのは簡単ではありません。その背景には、いくつかの心理的・組織的なブロックがあります。
まず大きいのは、「機能を削る=過去の判断ミスを認めること」という認識です。ある機能を機能削減の対象にすることは、その機能を推進した人や部署に対して「間違っていた」と言うことだと受け止められがちです。失敗学的には、本来は「仮説として実験し、結果から学ぶ」プロセスであるはずが、評価制度や組織文化によって「責任追及の文脈」になってしまうと、誰も機能の墓場にメスを入れようとしなくなります。
次に、成果が見えにくい仕事は評価されにくいという現実もあります。新機能のリリースはプレスリリースや社内報で可視化されますが、機能削減や機能の棚卸しは、目立ちにくい裏方の仕事になりがちです。フィーチャークリープを抑え、機能の墓場を片付けることは、長期的に見ればプロダクトの品質や開発速度を大きく改善しますが、その「貢献」が評価指標に反映されていないと、誰も積極的に取り組もうとしません。
そしてもう1つのブロックは、ステークホルダーの利害が複雑に絡み合っていることです。事業部門は売上と顧客満足を、現場は業務負荷とミス削減を、情報システム部門は安定運用とセキュリティを、そして経営は全体最適を考えています。「機能の墓場をなくすために機能削減をしたい」と言っても、それぞれの立場から見えるリスクとメリットが異なるため、合意形成に時間がかかりがちです。
このブロックを越えるためには、機能削減や機能の棚卸しを「特別な決断」ではなく、定期的に行う通常業務として位置づけることが重要です。例えば、四半期に一度は「増やす会議」ではなく「減らす会議」を公式に設定し、機能の棚卸しを行うことをルール化します。その際、「利用データ」「問い合わせデータ」「障害データ」「運用コスト」といった客観的な材料を前提に議論することで、「誰の責任か」ではなく「どの機能を残すと全体として最適か」という視点を持ちやすくなります。
心理的安全性をつくる一言
機能削減の議論を始めるときは、「これは過去の判断を責める場ではなく、プロダクトを次のフェーズに進めるためのアップデートです」と明言しておくのがおすすめです。機能の墓場の存在を「失敗」ではなく「次の学びの種」と捉え直すことで、フィーチャークリープの振り返りが前向きな対話になりやすくなります。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
実務で使える“機能削減フレームワーク”と棚卸しの手順
ここからは、現場でそのまま使える形に落とし込んだ「機能削減フレームワーク」と、機能の棚卸しの進め方を紹介します。ポイントは、感覚や好みではなく、共通の判断軸でフィーチャークリープの結果を見直すことです。
まず、各機能について「価値」と「コスト」、そして「戦略との整合性」と「リスク」の4つの観点で評価します。価値の評価では、利用頻度(アクセス数・実行回数)、アクティブユーザー数、その機能が関わる取引額や業務時間削減などを見ます。コストの評価では、開発・保守工数はもちろん、問い合わせ対応件数、マニュアル作成・教育、AIの場合は学習データ準備や再学習、監査対応なども含めて「トータルの負荷」を可視化します。
戦略との整合性については、「この機能は、プロダクトの北極星(価値提供の軸)に直結しているか」「今後3年の事業戦略と矛盾しないか」を確認します。たとえ利用頻度がそこそこ高くても、戦略上は縮小していきたい領域に紐づく機能であれば、長期的には機能削減や別プロダクトへの分離を検討すべきかもしれません。リスクの観点では、セキュリティ・個人情報保護・監査・説明責任といった側面から、「残し続けることで将来の負債にならないか」を考えます。特にAIの自動判断機能は、説明可能性や責任分界が曖昧なまま残すと、静かな機能の墓場であると同時に“大きなリスクの塊”にもなりかねません。
これら4つの観点を、簡易的なスコア(例えば1〜5)で評価し、次の4つの結論に分類します。「残す(強化する)」「凍結する」「別プロダクトに分離する」「捨てる(完全に機能削減する)」です。ここで重要なのは、「捨てる」だけでなく「凍結」や「分離」といった中間選択肢を設けることです。機能の墓場に埋もれた機能をすぐに削除するのが難しい場合でも、一旦新規開発対象から外したり、別の検証環境に移したりすることで、フィーチャークリープの拡大を止めることができます。
棚卸しの手順としては、以下のような流れが現実的です。まず、機能一覧と利用データ(アクセスログや実行回数)を用意し、「利用が少ない順」にソートします。次に、問い合わせや障害のデータを加え、「負荷が高いわりに価値が低そうな機能」をピックアップします。その上で、前述の4観点スコアリングを行い、分類結果ごとに対応方針とスケジュールを決めます。最後に、「いつまでに誰がどの機能を機能削減するのか」「ユーザーへの告知と移行はどう行うのか」を決め、リリースノートやFAQ、社内説明資料を準備します。
列に「機能名」「利用回数」「アクティブユーザー数」「問い合わせ件数」「開発・保守工数」「価値スコア」「コストスコア」「戦略整合スコア」「リスクスコア」「結論(残す/凍結/分離/機能削減)」を配置したスプレッドシートを用意すると、フィーチャークリープの実態と機能の墓場の全体像が一目で見えるようになります。
DX現場でのミニ事例:機能の墓場から抜け出したプロダクトたち
最後に、DX・AIプロジェクトの現場でよくある状況をもとに、機能の墓場から抜け出したミニ事例をいくつか紹介します。実在企業を特定しないように要素を再構成した「擬似ケース」ですが、多くの方が似た経験をされているはずです。
ケースA:誰も使いこなせない多機能ダッシュボード
ある企業では、複数部門の要望をすべて取り込んだ営業ダッシュボードを開発しました。売上推移、顧客セグメント分析、活動ログ、キャンペーン別指標など、画面は充実していたものの、実際には「トップページの2つのグラフしか見ていない」という状況でした。ログ分析から「よく使われている指標」を洗い出し、部門横断ワークショップで「意思決定に本当に必要な3指標」を定義。その他のウィジェットは段階的に機能削減し、必要な人だけがアクセスできる詳細画面に移しました。結果として、ダッシュボードの利用時間と満足度は増え、運用コストも削減されました。
ケースB:AI自動化が生んだ“二度手間”の機能の墓場
バックオフィスの業務効率化として、請求書の自動チェックAIを導入した企業では、精度を上げようとするあまりフィーチャークリープが発生しました。例外パターンごとに追加ルールを実装し続けた結果、現場は「AIの判定結果をすべて目視確認する」という二度手間に陥っていました。そこで、「AIは最終判断ではなく候補提示に徹する」「一定スコア以上の案件だけをAIに任せる」とルールを再設計し、それ以外の複雑な案件については人間の判断に戻しました。同時に、ほとんど使われていない設定項目や、精度の悪い自動判定機能を思い切って機能削減したことで、全体の処理時間が短縮され、担当者のストレスも減少しました。
ケースC:カスタマイズ要望に振り回された業務システム
ある業務システムでは、営業が顧客からの要望に応える形で個別機能を次々と追加し、プロダクトが機能の墓場になりかけていました。そこで、プロダクトチームは「標準機能」と「カスタム機能」を明確に切り分ける方針を打ち出し、フィーチャークリープの結果として生まれた複数の機能を整理しました。利用実態の薄いカスタム機能は段階的に機能削減し、今後の要望についても、「標準機能に取り込む基準」と「個別アドオンとして提供する基準」を明文化しました。この結果、ロードマップの見通しが立てやすくなり、開発チームはコア機能の改善に集中できるようになりました。
これらのケースに共通するのは、「増やす前提」から「増やしたうえで定期的に機能削減する前提」へと発想を転換したことです。機能の墓場は避けられない事故ではなく、フィーチャークリープを前提にした設計・運用をしてしまった結果です。機能削減や機能の棚卸しを通じて、「本当に使われている価値」にプロダクトを近づけていくことが、DXやAIプロジェクトを長く健全に続けるための鍵になります。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
まとめ:機能削減はプロダクトの「撤退」ではなく「進化」
本記事では、DX・AIプロダクトが「機能の墓場」になってしまう構造と、その裏側で静かに進行するフィーチャークリープについて整理してきました。機能が増えすぎたプロダクトを前にすると、「どこから手をつけてよいか分からない」「機能削減を提案すると反発されそう」という気持ちが先に立ちますが、機能の棚卸しと機能削減は、決して後ろ向きの作業ではありません。
むしろ、定期的な機能削減こそが、コアとなる価値を浮かび上がらせ、現場が安心して使い続けられるプロダクトへと進化させるためのプロセスです。そのためには、「声の大きい要望」をそのまま機能化しないこと、例外対応をすべてシステムに押し込まないこと、評価指標を「機能数」から「成果」にシフトすること、そして何よりも、機能削減をチームで議論できる心理的安全性をつくることが重要です。
今日からできる一歩としては、「この1年で増えた機能のうち、実際に使われているものはどれか」「利用が少ないが、運用負荷が大きい機能はどれか」を見える化することから始めてみてください。そして、小さな単位でも構わないので、フィーチャークリープの結果として生まれた機能の墓場を1つずつ片付けることで、プロダクト全体の見通しが少しずつ良くなっていきます。
機能削減に向き合うことは、自社のDX・AIプロジェクトの“過去の判断”と対話することでもあります。そのプロセスを通じて、「何を増やすべきか」「どこで増やすのをやめるべきか」という感度が磨かれていきます。そうした経験値は、新しいシステムやAIプロジェクトを立ち上げる際にも必ず活きてきます。機能の墓場を放置するのではなく、意識的な機能削減を通じて、プロダクトを次のフェーズへ進めていきましょう。
株式会社ソフィエイトのサービス紹介
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い







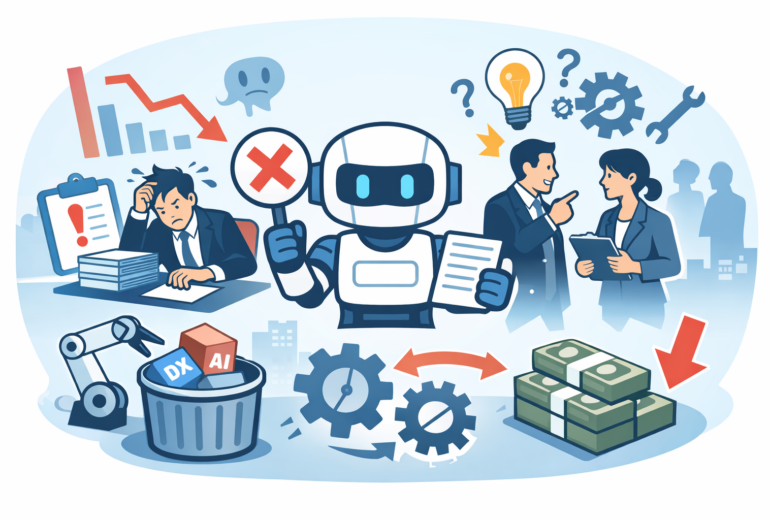



-770x520.png)








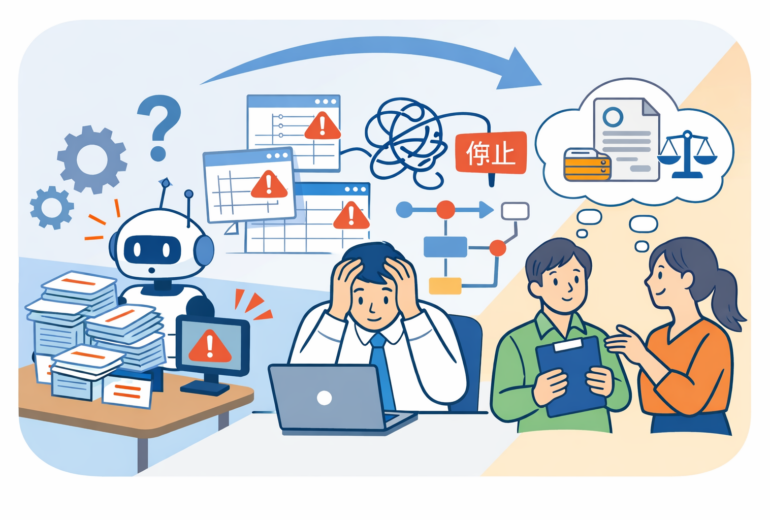



コメント