Contents
Difyで業務マニュアルを読み込ませてAIヘルプデスクを作る方法
なぜ今「AIヘルプデスク」と業務マニュアル活用なのか
多くの企業では、せっかく整備した業務マニュアルや社内マニュアルが、現場では十分に活用されていません。「どのフォルダにあるのか分からない」「検索しても欲しい情報がヒットしない」「読めば分かるが時間がかかる」といった理由から、結局Slackやメールで同じ質問が何度も飛び交い、担当者が即席ヘルプデスクのようになってしまいます。問い合わせ対応に追われて本来の業務が後回しになり、属人化も進む――PMやDX推進担当の方なら、一度は経験したことがある状況ではないでしょうか。
こうした「問い合わせ地獄」を抜け出すために注目されているのが、業務マニュアルをベースにしたAIヘルプデスクです。従来のFAQやチャットボットでは、想定された質問文にしか対応できず、「少し聞き方を変えると答えが返ってこない」という課題がありました。一方で生成AIを活用したAIヘルプデスクは、「経費精算の業務マニュアルの中で、出張旅費の上限を教えて」など、人間同士の会話に近い聞き方でも柔軟に理解し、関連する業務マニュアルの内容を要約して返答できます。
さらに重要なのは、AIが勝手に答えを作るのではなく、社内で正式に承認された業務マニュアルを根拠として回答する点です。「このAIヘルプデスクの回答はどのマニュアルに基づいているのか?」を明示できれば、コンプライアンスや監査の観点でも安心して利用できます。この「信頼できる根拠を示しながら答えるAIヘルプデスク」を、ノーコードで実現できるのがDifyです。Difyを使えば、現場が普段使っている業務マニュアルを読み込ませるだけで、短期間でAIヘルプデスクを立ち上げ、社内問い合わせを減らすことができます。
AIヘルプデスクは単なる「便利なツール」ではなく、問い合わせログから「どの業務マニュアルが分かりづらいか」「どのルールにグレーゾーンが多いか」をあぶり出すレンズにもなります。つまり、Difyで構築したAIヘルプデスクを起点に、業務マニュアルの品質向上とDX推進を同時に進めることができるのです。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
Difyで実現するノーコードAIヘルプデスクの全体像
Difyは、生成AIを使ったアプリケーションをノーコード/ローコードで構築できるプラットフォームです。ブラウザ上の管理画面から、チャットUI・業務マニュアルなどのナレッジ・ワークフローを組み合わせて、独自のAIヘルプデスクを素早く作れる点が特徴です。大きく分けると、「ナレッジ機能」と「アプリ(チャット/ワークフロー)」の二つが中核になります。
ナレッジ機能では、PDFやWord、Markdownなど多様な形式の業務マニュアルをアップロードすると、Difyが自動的にテキストを分割し、ベクトル検索用のデータとしてインデックス化します。ユーザーがAIヘルプデスクに質問すると、このナレッジから関連性の高いチャンク(文書の断片)が検索され、その内容を元に回答が生成されます。いわゆるRAG(検索拡張生成)という仕組みで、これにより「AIヘルプデスクが社外情報や誤情報に基づいて答える」リスクを抑えながら、自社の業務マニュアルに沿った回答が可能になります。
一方、アプリ側では、Difyの「Chatflow」や「Workflow」を使って、AIヘルプデスクの振る舞いをノーコードで定義します。たとえば、「ユーザーの質問を受ける」「ナレッジ検索を行う」「回答を生成し、根拠となる業務マニュアルの見出しとURLを添えて出力する」といった流れを、ノードをつなぐ感覚で構成できます。また、問い合わせカテゴリーに応じて別システムのAPIを呼んだり、人間の担当者にエスカレーションしたりする分岐も、同じくノーコードで組み込めます。
さらにDifyでは、ナレッジごとにメタデータやタグを設定できるため、「経理部向けの業務マニュアルだけを参照するAIヘルプデスク」「最新改訂日が一定期間内のマニュアルだけを優先するAIヘルプデスク」といった現実的な運用も容易です。クラウド版を使って素早く始めることも、自社環境にホストしてセキュリティ要件を満たすこともできるため、PMやDX担当は自社のルールに合わせて導入を検討できます。
Difyは「AIモデルそのものを開発するツール」ではなく、「LLMと業務マニュアル・ワークフローを組み合わせてAIヘルプデスクを構築するための土台」と捉えるとイメージしやすくなります。
業務マニュアルからAIヘルプデスクを作るDify実装ステップ
ここからは、業務マニュアルを起点にDifyでAIヘルプデスクを実装する手順を、現場でそのまま使えるレベルで整理します。いきなり全社展開を狙うのではなく、「問い合わせが多く、ルールが比較的明確なテーマ」から始めることが成功の鍵です。典型的には、経費精算、勤怠・休暇申請、アカウント発行、社内システム利用手順といった領域の業務マニュアルが候補になります。
ステップ1:対象業務と業務マニュアルの選定・整備
最初に、「どの問い合わせを減らしたいのか」「どの業務マニュアルがよく参照されるべきか」を明確にします。過去数ヶ月分のSlackやヘルプデスクチケットを眺め、件数の多いテーマを洗い出しましょう。その上で該当する業務マニュアルを棚卸しし、古い版をアーカイブし、情報が重複しているマニュアルは統合します。章立てを「目的」「対象者」「前提」「手順」「よくある質問」といった共通フォーマットに寄せておくと、後の検索精度が上がります。
ステップ2:Difyのナレッジに業務マニュアルを登録する
次に、Difyの管理画面で新しいナレッジベースを作成し、整備した業務マニュアルをまとめてアップロードします。アップロード後は、Difyが分割したチャンクをざっと確認し、「1チャンクあたりの情報量が多すぎないか」「見出しや箇条書きが変な位置で切れていないか」をチェックします。また、各業務マニュアルに対して「部署」「システム名」「文書種別」「改訂日」といったメタデータを付与しておくと、AIヘルプデスク側でのフィルタリングが容易になり、誤ったマニュアルを参照するリスクを減らせます。
ステップ3:AIヘルプデスク用チャットアプリの設計
ナレッジが準備できたら、DifyでAIヘルプデスク用のチャットアプリを作成します。プロンプトでは、「あなたは社内の業務マニュアルに基づいて案内を行うAIヘルプデスクです」と役割を明示し、業務マニュアル以外の情報に基づいて勝手に推測しないよう指示します。回答には必ず参照したマニュアル名と節番号、URLを含めるようにし、「情報が見つからない場合は無理に回答せず、人間への確認を促す」ルールも書き込みます。これにより、AIヘルプデスクが「それらしく見える誤答」を出すリスクを抑えられます。
ステップ4:テストシナリオの作成と検証
最後に、現場で実際に飛び交っている質問をもとに、テストシナリオを作成します。1テーマあたり50〜100問程度を目安に、Slackログや口頭での問い合わせを洗い出し、DifyのAIヘルプデスクに投げてみます。期待される回答とのギャップをスプレッドシートなどで管理し、「単純な誤答なのか」「業務マニュアル側の表現が分かりにくいのか」「ナレッジのタグ・メタデータ設計が原因なのか」を切り分けます。ここでの検証結果は、そのままマニュアル改善やDifyの再設定に生かすことができます。
1つの部署・1つの業務マニュアル群に絞ってAIヘルプデスクを立ち上げ、成功パターンをテンプレート化してから他部門に展開すると、プロジェクトがスムーズに進みます。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
運用と改善:AIヘルプデスクを「育てる」ための仕組み
DifyでAIヘルプデスクをリリースした後、成果を左右するのは「運用でどれだけ改善を回せるか」です。リリース直後はどうしても粗が出ますが、これは失敗ではなく、むしろ業務マニュアルやルールの改善ポイントが可視化された状態とも言えます。そこで、AIヘルプデスクと業務マニュアルの両方を継続的にブラッシュアップする仕組みを作りましょう。
まず重要なのが、問い合わせログの定期的なレビューです。Difyのログから、AIヘルプデスクが「答えられなかった質問」「曖昧な回答をした質問」「ユーザーから低評価がついた回答」を抜き出し、原因を分類します。マニュアルに記載がない場合は、業務担当と協議して業務マニュアルを更新する必要がありますし、記載はあるがAIが参照できていない場合は、チャンクの分割やタグ付け、プロンプトの改善が必要です。
次に、「業務マニュアル改訂とDifyナレッジ更新の連携」をルール化します。多くの組織では、マニュアル改訂時にAIヘルプデスク側のナレッジが放置されがちです。これを防ぐために、マニュアルの版管理フローに「Difyナレッジの更新」「AIヘルプデスクの再テスト」を組み込んでおきます。改訂日や版数をメタデータとして登録し、「最新版のみを参照するAIヘルプデスク」を実現すれば、誤案内のリスクを大きく下げられます。
ガバナンスの観点では、「AIヘルプデスクが答えてよい範囲」を明確にしておくことが大切です。法務・人事・経営判断に関わる領域は、人間へのエスカレーションを必須としたり、回答のトーンを慎重にしたりといったガードレールを敷きます。これはプロンプト上のルールだけでなく、DifyのWorkflowで分岐条件として実装し、「特定のキーワードが含まれる質問は自動的に担当者に転送する」といった仕組みを作ると安心です。
最後に、KPIとモニタリングです。「AIヘルプデスク経由で自己解決した割合」「問い合わせ件数の推移」「回答に対するユーザー満足度」「回答までの平均時間」などを四半期ごとにレビューすれば、経営層や他部門に対して投資対効果を説明しやすくなります。これらの数字をベースに、対象とする業務マニュアルの範囲を広げたり、Difyと他システムとの連携を強化したりと、次の一手を検討できます。
小さく始めて全社へ広げるロードマップとソフィエイトの支援
実務でAIヘルプデスクを導入する際には、「小さく始めて、うまくいった型を水平展開する」アプローチが現実的です。具体的には、バックオフィス部門や特定プロジェクトなど、限定された領域の業務マニュアルを対象に、DifyでAIヘルプデスクを構築し、1〜2ヶ月運用してみます。その間に、問い合わせ件数や対応時間の変化、現場からのフィードバックを集め、「この業務マニュアル構造ならAIヘルプデスクがうまく機能する」「この粒度だと回答が曖昧になりやすい」といった知見を溜めます。
その上で、第二フェーズとして対象範囲を広げていきます。たとえば、「勤怠・休暇」に続いて「経費精算」「社内システム利用」「セキュリティルール」といったテーマ別に業務マニュアルをDifyのナレッジに追加し、ひとつのAIヘルプデスクから順次対応範囲を広げる方法があります。または、「営業部門向けAIヘルプデスク」「開発部門向けAIヘルプデスク」のように、部門ごとにDifyアプリを分ける方法もあります。どちらにしても、最初に得られた成功パターンをテンプレート化しておくことで、展開が格段にスムーズになります。
一方で、PMやDX推進担当だけで、業務棚卸し・業務マニュアルの再設計・Difyの設計・社内合意形成までを一気に進めるのは負荷が大きいのも事実です。そこで、外部パートナーをうまく活用することで、プロジェクトの立ち上がりを加速できます。株式会社ソフィエイトでは、Difyを活用したAIヘルプデスク構築の経験を活かし、「どの業務マニュアルから手を付けるべきか」「AIヘルプデスクの役割をどう定義するか」「どこまでノーコードで対応し、どこから先をシステム連携とするか」といった検討を、初期フェーズから伴走することが可能です。
お問い合わせ・無料相談はこちら
「この要件だとシステム開発費用はどのくらい?」「見積もりが妥当か不安」「コスト削減の余地はどこ?」といったご相談に対し、概算だけでなく、見積もりの前提整理や段階リリースの切り方まで一緒に整理します。社内説明に使える“発注メモ”の形に落とし込むことも可能です。
業務マニュアルを活かしたDifyベースのAIヘルプデスク導入についても、お気軽にお問い合わせください。
また、ソフィエイトのサイト内の関連記事(たとえば「社内FAQの設計方法」「議事録自動化におけるDify活用事例」など)とあわせて読んでいただくことで、AIヘルプデスクにとどまらない業務全体のDX像を描きやすくなります。まずは小さな範囲から着手し、Difyと業務マニュアルを軸に社内の知識循環を整えていくことが、長期的な競争力につながっていくはずです。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
まとめ
本記事では、業務マニュアルを土台にDifyでAIヘルプデスクを構築し、社内問い合わせを減らすアプローチを解説しました。ポイントは、「AIモデルを一から作る」のではなく、「既に存在する業務マニュアルを、Difyを通じて使いやすい形で現場に届ける」発想に切り替えることです。問い合わせログから現場のつまずきを可視化し、マニュアルとAIヘルプデスクの両方を改善していくことで、属人化やコミュニケーションコストといった根強い課題にも手を打てます。
PMやDX推進担当の方にとって、最初の一歩は「対象業務と業務マニュアルの選定」と「Difyでの小さなPoC」です。完璧な設計を目指して立ち止まるよりも、小さく始めてフィードバックを得ながら改善していく方が、結果として高い精度と現場への浸透を実現できます。もし「どこから手をつければよいか分からない」「社内の合意形成が難しそう」と感じた場合は、ぜひソフィエイトの無料相談も活用しながら、自社に合ったAIヘルプデスクと業務マニュアル活用の形を一緒に探っていきましょう。
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い






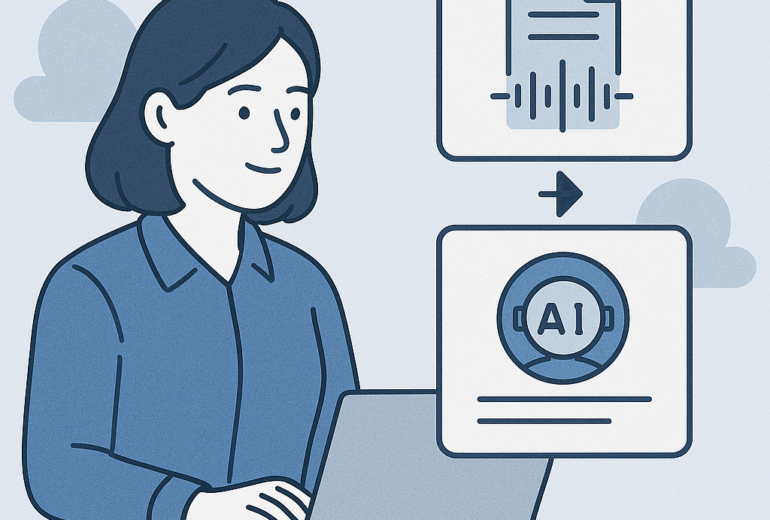














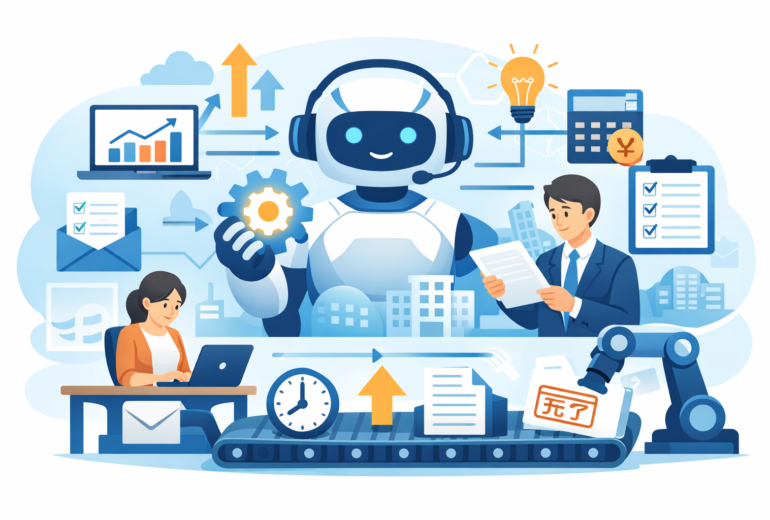


コメント