Contents
ETL / ELTとクラウドDWHで、「バラバラな数字」から卒業する
売上データは会計ソフト、顧客情報はCRM、アクセス解析は別ツール、予算はExcel…。中小企業でも、データはすでに社内のあちこちに散らばっています。ところが会議のたびに各部署が「うちの数字」を持ち寄るため、同じ売上なのに金額が合わない、最新データが反映されていない、といったことが起こりがちです。
こうした状況から抜け出すための土台が、データを集めて整え、ひとつの基盤にまとめる仕組み=ETL / ELT とクラウドDWHによるデータ基盤です。これを整えることで、毎月の集計作業を減らし、「どの数字を見ればいいか」で迷わない状態に近づきます。
本記事では、まずETLとELTの違いをわかりやすく整理し、そのうえで代表的なクラウドDWHである BigQuery Redshift Snowflake の特徴と選び方を解説します。AIやITに詳しくない方でも、自社でどのようにデータ基盤を整えるべきかイメージできるよう、実務に沿った形で説明していきます。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
ETLとELTの基本:どこで「加工」するかの違いだけ
最初に押さえておきたいのは、ETLもELTも、やっていること自体は「データを取り出し、加工し、保存する」という点で同じだということです。違いはその順番と、どこで加工するかにあります。
ETL(Extract → Transform → Load)は、業務システムや専用ツール側でしっかり変換・クレンジングを行ってから、データウェアハウスに格納する方式です。古くからある手法で、銀行や基幹系システムなど「絶対に間違えてはいけない」領域では今も主流です。項目を厳密に定義し、変換ロジックを作り込み、テストを行ってから本番運用に入るため、品質は安定しやすい反面、変更や追加には手間がかかります。
一方 ELT(Extract → Load → Transform)は、まずは元の形のまま BigQuery Redshift Snowflake などのクラウドDWHにロードし、その上でSQLや変換ジョブを使って加工します。クラウドDWHの計算能力を前提にしているため、とりあえず全データを集約しておき、後から必要に応じて整えていくスタイルに向きます。分析の切り口を柔軟に変えたいマーケティング部門や、まだデータ基盤の要件が固まっていない成長企業に適しています。
注意したいのは、どちらの方式を選ぶ場合でも「変換ルールの見える化」が不可欠だということです。ETLではツールの設定画面やスクリプトがブラックボックスになりがちですし、ELTではSQLが担当者のローカルPCの中にだけ存在する、という状態になりがちです。変換ルールは必ずリポジトリやドキュメントにまとめ、誰でも追える状態を作ることが、長期運用の鍵になります。
Tips:ETLとELTをきっちり「二者択一」にしない
実務では、基幹システムから会計向けデータを作る部分はETLでがっちり固め、マーケティングデータやログデータはELTで柔軟に扱う、というようにハイブリッドにするケースが多くあります。「すべてETL」「すべてELT」と決めつけず、データの性質ごとに最適な組み合わせを検討するのがおすすめです。
BigQuery / Redshift / Snowflake:3大クラウドDWHの特徴をざっくり把握する
次に、ETL ELT の受け皿となるクラウドDWHとしてよく候補に上がる、BigQuery Redshift Snowflake の違いを整理します。ここでは細かな仕様ではなく、「どのような企業・利用シーンと相性が良いか」に絞って解説します。
BigQuery:スプレッドシート感覚で伸ばせるデータ基盤
BigQueryはGoogle Cloudのデータウェアハウスで、クエリごとの従量課金、サーバーレスという特徴を持ちます。すでにGoogle WorkspaceやLooker Studioを使っている企業にとっては、連携がスムーズで学習コストも低めです。
シンプルなELT構成で、「まずは売上や広告データを集約し、スプレッドシートやBIから分析する」といったスモールスタートに向きます。
一方で、クエリを打ちすぎると料金が跳ね上がる可能性があるため、ビューの設計やクエリの最適化が重要です。「誰でも自由に叩いていい」状態にしてしまうと、気づいたら月末に請求額が増えていた、ということもあり得ます。
Redshift:AWS中心のシステム構成と相性の良い王道DWH
RedshiftはAWSのDWHサービスで、EC2やS3、各種マネージドサービスと組み合わせた統合的なデータ基盤を構築しやすい点が強みです。既に社内システムをAWS上に載せている企業では、ネットワークやセキュリティ設計を含めて一体的に管理できます。
Redshiftはクラスタ(サーバー)のサイズや台数を事前に決めておく必要があり、その分容量と性能の見積もりに少し慎重さが求められます。ただし、ワークロードが読める業務システムや定型レポート中心のデータ基盤では、コストをコントロールしやすい選択肢です。
Snowflake:マルチクラウド時代を見据えた柔軟なデータ基盤
Snowflakeは、クラウドベンダーに依存しないDWHとして設計されており、AWS・Azure・GCPのどこでも動かせるのが特徴です。コンピュートとストレージが完全に分離しており、ETL ELT のバッチ処理用と分析用に計算リソースを分けることもできます。
複数グループ会社でデータ基盤を共通化したい場合や、将来的にクラウドをまたいで運用したい場合などには、Snowflakeが選択肢に上がります。一方、月額課金やクレジットの考え方がやや独特なため、最初はパートナーと一緒に料金設計を行うことをおすすめします。
補足:どれが「一番良い」わけでもない
BigQuery Redshift Snowflake はいずれも成熟したサービスです。「どれが一番高性能か」よりも、自社で既に使っているクラウドやSaaSとの相性、運用チームのスキルセット、サポートしてくれるパートナーの有無など、周辺条件で選ぶほうが現実的です。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
自社に合う「ETL / ELT × DWH」の組み合わせを考える
では、実際に自社のデータ基盤を設計するとき、どのように組み合わせを決めればよいのでしょうか。ここでは、検討の際に使えるチェックポイントを整理します。
1. データ量と更新頻度の目安をつかむ
まずは「どれくらいのデータが、どの頻度で増えるのか」をざっくり把握します。月次レポート中心で、対象データも売上と顧客マスタ程度であれば、ELTでBigQueryに集約するだけでも十分なデータ基盤になり得ます。一方、受注から出荷、請求までを日次で締めたいような業務では、RedshiftやSnowflakeでスキーマをしっかり設計し、ETLツールを使って変換ルールを固定しておくほうが安全です。
2. 社内のITスキル・体制を冷静に評価する
次に、SQLやPythonを書ける人がどの程度いるか、クラウドの運用経験があるかを確認します。担当者が一人しかいない場合、あまりに複雑なETL ELT 構成にすると、その人が異動・退職したときにデータ基盤が止まってしまいます。「最小限の人員でも運用できるシンプルさ」を基準に設計することが重要です。
例えば、マーケ担当者が多少SQLを書けるのであれば、ELTでSnowflakeにデータを貯め、dbtのようなツールで変換ロジックを管理する構成も選択肢になります。逆にSQLを誰も書けない場合は、変換部分は外部パートナーに任せつつ、レポート閲覧はノーコードBIに寄せるなど、役割分担をはっきりさせると運用しやすくなります。
3. 既存のクラウド環境との整合性をとる
すでにGCPを利用しているならBigQuery、AWS中心ならRedshift、マルチクラウドを見据えるならSnowflake、というのが基本的な考え方です。データ基盤は長く使うインフラなので、ネットワークやセキュリティ、請求管理をシンプルに保つことが、結果的にコスト削減と安定運用につながります。
チェックリスト例:検討時に決めておきたいこと
- このデータ基盤で、誰がどの数字を見て判断したいのか
- 「公式な数字」として扱う指標は何か(売上・利益・受注数など)
- データの更新頻度(リアルタイムか、日次か、月次か)
- SQLを書ける人・ETL ELT を触れる人は社内に何人いるか
- 既に利用しているクラウド(GCP / AWS / その他)はどれか
スモールスタートで進めるETL / ELTプロジェクトの実行ステップ
ETL ELT とクラウドDWHによるデータ基盤は、一度で完璧なものを作ろうとすると必ず行き詰まります。成功している企業の多くは、1〜3か月で終わる小さなプロジェクトから始め、少しずつ範囲を広げているのが実態です。ここでは、典型的なスモールスタートの流れを紹介します。
ステップ1:テーマをひとつに絞る
まずは「広告費と売上の関係を毎朝確認できるようにしたい」「各拠点ごとの売上ランキングを自動集計したい」など、具体的なテーマを一つ決めます。このとき、「全社のデータを全部入れたい」と範囲を広げすぎないことがポイントです。テーマが決まれば、関係するシステムやファイルを洗い出し、どのテーブルにどの項目を保存するか、簡単な図にして整理します。
ステップ2:データ連携と変換ロジックを組む
次に、ETL ELT の処理フローを作ります。ELTであれば、まずSaaSやデータベースからBigQuery Redshift Snowflake へデータをロードするジョブを作り、その後ビューや変換テーブルを定義していきます。ETLであれば、ツールやスクリプトで変換処理を記述し、テストを重ねてから本番バッチに組み込みます。
この段階で大事なのは、「手作業でやるとしたらどういう手順になるか」を言語化してから、自動化に落とすことです。手作業フローが曖昧なままETL ELT のロジックを書き始めると、後から仕様変更が頻発し、プロジェクトが長期化してしまいます。
ステップ3:レポート・ダッシュボードを作り、実際に使ってもらう
データがデータ基盤に流れたら、最後にレポートやダッシュボードを作成します。最初は見た目の作り込みよりも、「毎朝最新の数字が出ること」「会議で使っているExcelを置き換えられること」を重視しましょう。
現場のマネージャーや経営陣に実際に触ってもらい、「この集計軸もほしい」「この項目はいらない」といったフィードバックを受けながら、少しずつブラッシュアップしていきます。
ステップ4:運用ルールとトラブル対応の体制を整える
最後に、データ基盤を継続的に運用するためのルールを整えます。例えば、
- バッチが失敗したときに誰にアラートが飛ぶか
- 新しいシステムを導入したとき、ETL ELT にどう組み込むか
- 権限を付与・剥奪する手順をどうするか
などを決めておくと、トラブルが起きても慌てずに対応できます。ここまで整って初めて、「データ基盤が業務フローの一部として根付いた」と言える状態になります。
3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら
まとめ:小さく始めて「育てる」データ基盤づくりを
本記事では、ETL ELT の違いと、BigQuery Redshift Snowflake をはじめとするクラウドDWHの特徴、自社に合ったデータ基盤の選び方について解説しました。ポイントは、完璧な構成を一度で作ろうとせず、小さく始めて少しずつ育てていくことです。
データ基盤は、単なるITプロジェクトではなく、会社全体の意思決定の土台を整える取り組みです。ETL ELT を通じてデータを整理し、BigQuery Redshift Snowflake のようなDWHに集約することで、数字に基づいた議論や、素早い軌道修正がしやすくなります。一方で、ツールや方式の選定だけに目を奪われると、「誰のどんな意思決定を支えるためのデータ基盤なのか」という本来の目的を見失いがちです。
もし社内に専門人材が少なく、どこから手をつけるべきか悩まれている場合は、要件整理やツール選定の段階から外部パートナーをうまく活用するのも良い選択です。適切な支援を受けつつ、自社内にデータ基盤を理解する人を育てていくことで、長期的に価値を生み続ける仕組みを築くことができます。
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い











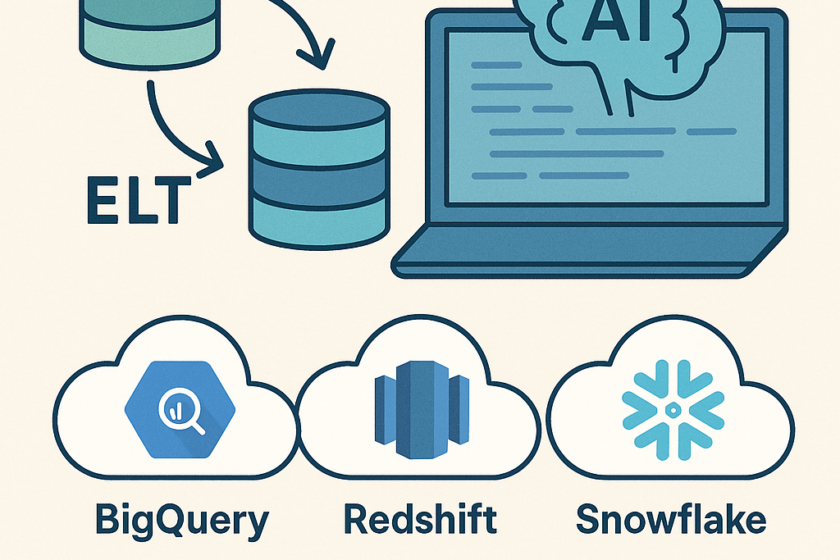











コメント