Contents
はじめに:なぜ今「ベクトルDB」が注目されているのか
ChatGPTや生成AIの活用が進む中で、多くの中小企業が直面している課題があります。それは「社内に蓄積された文書・データをどう効率的に活用するか」ということです。顧客からの問い合わせ対応、営業支援、社内ナレッジの共有――これらの業務で、従来のキーワード検索では対応しきれない「意味の近さ」を理解した検索が求められています。
従来のデータベース(MySQLやPostgreSQLなど)は、在庫管理や受注データのような構造化された情報の管理には最適ですが、メール本文や議事録、提案書といった「言葉のデータ」を「意味的に近い」という観点で検索することは苦手としています。例えば「顧客からの問い合わせに似た過去の回答例を探したい」「この案件に近い過去の提案書を参考にしたい」といった要望に対して、単純なキーワード一致では適切な情報を見つけられないケースが多々あります。
この課題を解決するのがベクトルDB(Vector Database)です。文章や画像を数値ベクトルに変換し、「意味の近さ」を計算することで、従来の検索では見つけられなかった関連情報を高速で引き出すことができます。中小企業にとっても、顧客対応の効率化、営業支援の強化、社内ナレッジの活用といった具体的な業務改善に直結する技術として注目されています。
代表的なベクトルDBとして、Pinecone、Weaviate、Qdrantの3つが挙げられます。これらは中小企業でも導入可能で、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。本記事では、これらの製品の違いを理解し、自社に最適なベクトルDBを選定するための実践的なガイドをご紹介します。
- 顧客からの問い合わせに対する回答品質の向上
- 営業担当者の提案書作成時間の短縮
- 社内ナレッジの横断的な活用と共有
- FAQやマニュアルの自動更新・最適化
- 過去の成功事例や失敗事例の効率的な検索
ベクトルDBの基本:通常のDBとの違いをシンプルに理解する
ベクトルDBの仕組みを理解するために、まず従来のデータベースとの違いを整理しましょう。従来のRDB(リレーショナルデータベース)は、表形式で整理されたデータを「完全一致」や「部分一致」で検索するのが得意です。例えば「商品名に”ノートPC”が含まれる商品を検索する」「価格が10万円以下の商品を抽出する」といった検索は、RDBが最も効率的に処理できます。
一方で、ベクトルDBが得意とするのは「意味的な類似性」による検索です。これは文章や画像をEmbedding(埋め込み)という技術を使って、数百〜数千次元の数値ベクトルに変換することで実現します。例えば「ノートPCの購入を検討している」という文章と「ラップトップコンピュータの選び方について」という文章は、人間には似た意味だと理解できますが、従来のデータベースでは「ノートPC」と「ラップトップ」という異なるキーワードとして扱われてしまいます。
ベクトルDBでは、これらの文章を数値ベクトルに変換し、ベクトル間の距離(コサイン距離やユークリッド距離)を計算することで「意味的に近い」文章を特定できます。つまり、「顧客からの質問に似た過去の回答例を自動で引き出す」「この提案書に近い過去の事例を検索する」といった、従来では困難だった検索が可能になります。
実務的な活用例として、以下のようなシーンが考えられます。営業担当者が新しい案件の提案書を作成する際、過去の類似案件の提案書や価格設定をベクトルDBで検索すれば、短時間で参考資料を収集できます。また、カスタマーサポートでは、顧客からの問い合わせに対して、過去の類似事例や回答例を即座に提示することで、回答品質の向上と対応時間の短縮を図れます。
Embedding(埋め込み)とは
文章や画像を数値ベクトルに変換する技術です。例えば「今日は良い天気ですね」という文章は、[0.2, -0.8, 0.5, 0.1, …]のような数百次元の数値配列に変換されます。似た意味の文章は似たベクトル値になり、ベクトル間の距離計算で類似性を判定できます。
ベクトルDBのもう一つの特徴は、ハイブリッド検索が可能なことです。これは「意味検索(ベクトル)」と「キーワード検索(従来の検索)」を組み合わせることで、より精度の高い検索結果を得られる仕組みです。例えば「営業部の提案書で、AI活用に関する内容」という検索では、「営業部」や「AI活用」といったキーワードで絞り込みつつ、意味的に類似した提案書を並行して検索できます。
代表的なベクトルDB3選:それぞれの特徴と向いている企業
ベクトルDBの導入を検討する際、まず理解しておくべきは「完璧な製品は存在しない」ということです。それぞれの製品が異なる強みと特徴を持っており、自社の要件や運用体制に合わせて選択する必要があります。ここでは、中小企業でも導入しやすい3つの代表的なベクトルDBについて、それぞれの特徴と向いている企業像を詳しく解説します。
Pinecone:運用の安心感を重視する企業向け
Pineconeは、完全マネージド型のクラウドサービスとして提供されているベクトルDBです。最大の特徴は、サーバー管理やインフラ構築が一切不要で、数分で使い始められることです。環境構築から指数の作成、データ投入、検索実行まで、すべてがクラウド上で完結するため、IT部門のリソースが限られている中小企業でも安心して導入できます。
Pineconeの技術的な強みは、ハイブリッド検索とメタデータフィルタの実装が充実していることです。ハイブリッド検索では、ベクトル検索(意味検索)とスパース検索(キーワード検索)を組み合わせることで、より精度の高い検索結果を得られます。また、メタデータフィルタにより「部署=営業部」「作成日=直近3か月」といった条件で絞り込みながら、意味的な類似性を考慮した検索が可能です。
セキュリティ面でも、Pineconeはエンタープライズレベルの対応を提供しています。プライベートネットワーク、顧客管理鍵、監査ログなどの機能に加え、SOC 2、ISO 27001、GDPR、HIPAAといった国際的なセキュリティ基準への対応姿勢を公開しています。これにより、医療・金融など規制の厳しい業界での審査にも耐えやすいのが現実的な利点です。
一方で、完全SaaS型であるがゆえの制約もあります。細かなインフラ最適化や極端なコストチューニングの自由度は限定的で、データの保管場所や処理方法についても、Pineconeが提供する範囲内での選択となります。また、コスト面では他の選択肢と比較してやや高めになる傾向があります。
- IT部門のリソースが限られている
- セキュリティ基準が厳しい業界(医療・金融など)
- 失敗しない導入を重視する
- 運用の安定性を最優先とする
- 小規模なPoCから本格導入まで一本化したい
Weaviate:検索体験の作り込みとAPI表現力を重視する企業向け
Weaviateは、オープンソースを起点としたベクトルDBで、クラウドサービスとオンプレミス運用の両方に対応しています。最大の特徴は、ハイブリッド検索の実装が明快で、キーワードの厳密一致と意味の近さを重み付けで融合できることです。これにより、従来の検索システムとAIを活用した意味検索を自然に統合できます。
API設計の柔軟性もWeaviateの強みです。REST APIとGraphQLの両方に対応しており、既存のシステムとの統合や段階的な高度化がしやすい設計になっています。特に、GraphQLによる柔軟なクエリ表現により、複雑な検索条件や関連データの取得を効率的に処理できます。また、モジュール式のベクトライザ連携により、OpenAI、Hugging Face、Cohereなど、様々なAIモデルとの連携が可能です。
クラウドサービスでは、サーバーレスを含む柔軟な課金体系を提供しており、使用量に応じた従量課金でコストを最適化できます。エンタープライズ向けには、SOC 2やHIPAA対応の強化版も提供されており、セキュリティ要件の高い環境でも利用可能です。
ただし、設計の幅が広いぶん、学習コストは相応に発生します。オープンソース版での内製運用も可能ですが、適切な設計や運用には一定の技術力が必要になります。また、コミュニティや情報は充実していますが、日本語でのサポートやドキュメントは限定的な場合があります。
Weaviateのハイブリッド検索の仕組み
BM25(従来のキーワード検索アルゴリズム)とベクトル検索を組み合わせ、それぞれのスコアを重み付けで融合します。例えば「AI活用」というキーワードで検索する際、BM25で「AI活用」という文字列を含む文書を抽出しつつ、ベクトル検索で意味的に類似した文書も並行して検索し、最終的なランキングで統合します。
Qdrant:コスト最適化と展開の自由度を重視する企業向け
Qdrantは、Rust言語で実装された高性能なベクトルDBで、オープンソース、クラウド、ハイブリッドクラウドと様々な展開形態に対応しています。最大の特徴は、HNSW索引に基づく高性能な近傍探索と、JSONペイロードによる柔軟な属性フィルタが実務に強い武器であることです。
技術的な強みとして、高次元ベクトルの量子化によるメモリ・ストレージの圧縮が挙げられます。これにより、コストとレイテンシの両立を図れ、特に大規模なデータセットを扱う場合の効率性が高くなります。また、Dockerコンテナでの簡単な起動や、Kubernetesでのスケーラブルな運用も可能で、既存のインフラ環境に柔軟に組み込めます。
展開の自由度もQdrantの大きな利点です。マネージドのQdrant Cloudに加え、ハイブリッドクラウドやプライベートクラウドも提供しており、データ主権や閉域要件に合わせやすい設計になっています。セキュリティ面では、SOC 2 Type IIの取得が公表されており、APIキー認証などの運用機構も用意されています。
コスト面でも、オープンソース版を利用すればライセンス費用が不要で、自社サーバーやクラウド環境での運用により、長期的なコスト最適化が可能です。ただし、内製運用には一定の技術力が必要で、初期の学習コストや運用負荷は考慮する必要があります。
総じて、Qdrantは「コスト最適化」「展開場所の自由度」「OSSでの内製」を重視する企業に向いています。特に、技術的なリソースが確保でき、長期的な運用を見据えた導入を検討している中小企業にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
3つのベクトルDBを比較:選び方の基準と実践的な判断方法
3つのベクトルDBの特徴を理解したところで、実際にどれを選ぶべきかを判断するための基準を整理しましょう。重要なのは「どれが一番優れているか」ではなく「どれが自社の要件に最も合うか」という視点で考えることです。
選定の起点となるのは「どの業務KPIを改善したいか」です。ベクトルDBの導入は、単なる技術導入ではなく、業務改善のための投資です。例えば「顧客対応の平均時間を30%短縮したい」「営業提案書の作成時間を半減させたい」「社内ナレッジの活用率を2倍にしたい」といった具体的な目標があることで、適切な製品選定と効果測定が可能になります。
技術的な選定基準として、以下の5つの要素を総合的に評価することをお勧めします。
データ規模は、扱う文書の量と更新頻度を指します。小規模なPoC(概念実証)から始める場合は、どの製品でも対応可能ですが、将来的な拡張性を考慮する必要があります。Pineconeは大規模データの処理に優れていますが、WeaviateやQdrantも適切な設計により大規模化に対応できます。
問い合わせ同時実行数は、システムの応答性とスケーラビリティに関わります。顧客向けのFAQシステムや営業支援ツールとして利用する場合、同時アクセス数の増加に対応できるかが重要です。Pineconeは自動スケーリング機能により、急激な負荷増加にも対応できます。
更新頻度は、データの鮮度とリアルタイム性を左右します。営業提案書や顧客情報のように頻繁に更新されるデータを扱う場合、リアルタイムでの更新と検索が可能かどうかが重要です。Weaviateは柔軟なスキーマ変更とリアルタイム更新に対応しており、Qdrantも高速な書き込み処理が特徴です。
必要SLAは、システムの可用性と応答時間の保証レベルです。特に顧客向けサービスとして利用する場合、99.9%以上の可用性や1秒以内の応答時間といった要件を満たす必要があります。PineconeはエンタープライズレベルのSLAを提供していますが、WeaviateやQdrantも適切な設計により高可用性を実現できます。
社内の運用体制は、技術的なリソースと運用負荷の配分です。完全マネージド型のPineconeは運用負荷が最小限ですが、WeaviateやQdrantのオープンソース版を内製運用する場合は、技術者の確保や継続的な学習が必要になります。
- Pinecone:審査・運用の安心感を優先する企業
- Weaviate:検索体験の作り込みやAPI表現力を重視する企業
- Qdrant:コスト最適化と展開の自由度を重視する企業
最終的な判断は、これらの要素をテーブル化し、2週間単位のPoC(概念実証)で数値比較するのが実務的です。PoCでは、実際の業務データを使用して、検索精度、応答速度、運用負荷などを測定し、投資対効果を明確にします。評価指標としては「回答までの時間」「正答率」「人手修正時間」「利用率」の4つが重要で、これらが改善すれば、サポート負荷の軽減や商談スピードの向上に直結します。
中小企業での導入シナリオ:具体例でイメージする実践的な活用方法
ベクトルDBの導入を検討する際、多くの中小企業が「具体的にどのような業務改善が期待できるのか」という点で迷いがちです。ここでは、実際の業務シーンを想定した具体的な活用例と、段階的な導入ステップについて詳しく解説します。
営業支援:過去の提案書やメール履歴から類似案件を検索
営業業務において、ベクトルDBが最も効果を発揮するのは、過去の提案書やメール履歴からの類似案件検索です。従来の営業支援では、担当者の経験や記憶に依存して「似たような案件はなかったか」「どのような価格設定で提案したか」を調べることが多く、効率性と網羅性の両面で課題がありました。
ベクトルDBを活用した営業支援では、過去の提案書、メール履歴、商談メモなどをEmbeddingし、新しい案件の要件と意味的に類似した過去事例を自動で検索できます。例えば「製造業向けのAI導入支援」という案件に対して、「製造業」「AI活用」「業務効率化」といったキーワードだけでなく、提案内容や課題設定の意味的な類似性を考慮した検索が可能になります。
具体的な実装手順としては、まず既存の提案書やメール履歴を適切なサイズのチャンク(段落単位)に分割し、各チャンクにメタデータ(作成日、担当者、業界、案件規模など)を付与します。次に、これらのチャンクをEmbeddingしてベクトルDBに格納し、検索用のクエリを作成します。営業担当者は、新しい案件の要件を入力するだけで、類似した過去事例や提案内容を即座に参照できます。
この活用により期待できる効果は、提案書作成時間の短縮、提案品質の向上、過去の成功事例の活用促進などです。特に、経験の浅い営業担当者にとって、ベテラン担当者の過去事例を効率的に学習できる機会となり、営業チーム全体のスキル向上にも寄与します。
顧客対応:FAQやマニュアルをベクトルDBに格納し、AIチャットボットに接続
顧客対応業務では、FAQやマニュアル、過去の問い合わせ記録をベクトルDBに格納し、AIチャットボットと連携することで、回答品質の向上と対応時間の短縮を図れます。従来のFAQシステムでは、顧客の質問と事前に登録された質問の完全一致や部分一致で検索するため、「似たような質問だが表現が異なる」場合に適切な回答を見つけられない問題がありました。
ベクトルDBを活用した顧客対応システムでは、顧客の質問を意味的に理解し、最も適切な回答例やマニュアルを自動で提示できます。例えば「商品の返品方法について教えてください」という質問に対して、「返品・交換について」「商品の返品手続き」「返品期限について」といった関連情報を、意味的な類似性に基づいて検索し、包括的な回答を提供できます。
実装のポイントは、FAQやマニュアルの適切なチャンク化と、メタデータの充実です。見出しや章の区切りで適切に分割し、各チャンクに「対象商品」「対象顧客」「関連業務」などのメタデータを付与することで、より精度の高い検索が可能になります。また、過去の問い合わせ記録も併せて格納することで、実際の顧客の表現パターンに近い回答例を提供できます。
このシステムにより、顧客対応の品質向上、担当者の負荷軽減、24時間対応の実現などが期待できます。特に、専門知識が不足している新入社員や、繁忙期の人員不足時において、一貫した品質の顧客対応を維持できる点が大きなメリットです。
社内ナレッジ活用:議事録や報告書から関連情報を横断検索
社内ナレッジの活用において、ベクトルDBは議事録、週報、ノウハウ集など、様々な文書から関連情報を横断的に検索することを可能にします。従来の文書管理システムでは、ファイル名やフォルダ構造に依存した検索が中心で、「今の課題に関連する過去の議論や事例」を効率的に見つけることが困難でした。
ベクトルDBを活用した社内ナレッジシステムでは、例えば「在庫管理の効率化」という現在の課題に対して、「在庫管理」「効率化」「業務改善」といったキーワードだけでなく、過去の議事録や報告書で議論された内容、実際に実施された改善施策、その結果や効果など、意味的に関連する情報を横断的に検索できます。
実装において重要なのは、文書の適切な前処理と、継続的な更新・メンテナンスです。議事録や報告書は、議題ごとや議事項目ごとに適切にチャンク化し、開催日、参加者、議題、決定事項などのメタデータを付与します。また、新規文書の自動Embeddingや、定期的な品質評価(ヒット率や手戻り率)を実施することで、システムの精度を継続的に向上させることができます。
この活用により期待できる効果は、意思決定の質向上、業務効率の改善、知識の継承・共有の促進などです。特に、異動や退職による知識の流出を防ぎ、組織全体の知見を効率的に活用できる点が、中小企業にとって大きなメリットとなります。
導入の成功ポイント
最初から完璧を目指さず、対象を一つに絞って2〜4週間のPoCを回すことで、投資判断が明確になります。評価指標は「回答までの時間」「正答率」「人手修正時間」「利用率」の4つで、これらが改善すれば、サポート負荷の軽減や商談スピードの向上に直結します。
導入前に知っておくべき注意点と実装の勘所
ベクトルDBの導入を成功させるためには、技術的な実装だけでなく、運用面での考慮事項も重要です。ここでは、導入前に知っておくべき注意点と、効果的な実装のための勘所について詳しく解説します。
データの前処理:効果の差を決める重要な要素
ベクトルDBの効果は、データの前処理の質によって大きく左右されます。適切な前処理を行わないと、検索精度が低下し、期待した効果が得られない可能性があります。前処理の中心となるのは、文書のチャンク化とメタデータの付与です。
チャンク化では、文書を適切なサイズの段落に分割することが重要です。一般的には、200〜1000文字程度のチャンクが推奨されますが、これは文書の性質や用途によって調整が必要です。見出しや章の区切りを基準に分割することで、文脈を保ったまま検索可能な単位を作成できます。また、表や図表を含む文書では、それらを適切にテキスト化してチャンクに含めることも重要です。
メタデータの付与は、検索精度と実用性を向上させる重要な要素です。作成日、作成者、部署、顧客種別、文書種別などの基本的な情報に加え、業務上重要な属性(例:案件規模、業界、技術分野など)も含めることで、より精密な絞り込み検索が可能になります。メタデータは、後から追加・変更することも可能ですが、初期設計段階で適切に設計しておくことが重要です。
データのクリーニングも前処理の重要な要素です。不要な改行や特殊文字の除去、表記ゆれの統一、重複データの除去などを行うことで、Embeddingの品質と検索精度を向上させることができます。特に、社内文書では略語や専門用語の表記ゆれが多く発生するため、辞書やルールベースによる正規化が効果的です。
セキュリティ面での考慮事項
ベクトルDBの導入において、セキュリティ面での考慮は不可欠です。特に、社外のクラウドサービスを利用する場合は、データの暗号化、アクセス制御、監査ログなどの実装可否を事前に確認する必要があります。
データの暗号化については、転送時(TLS/SSL)と保存時(暗号化)の両方で適切な実装が行われているかを確認します。また、APIキーやアクセストークンの管理、IPアドレスによるアクセス制限、多要素認証などの認証・認可機能も重要です。特に、顧客情報や機密性の高い社内情報を扱う場合は、これらの機能が適切に実装されているかを確認してください。
監査ログは、セキュリティインシデントの調査やコンプライアンス要件の満足に重要です。データの読み取り、書き込み、削除などの操作ログが適切に記録され、必要に応じて分析・監査が可能であるかを確認してください。また、データのバックアップと復旧機能も、事業継続性の観点から重要です。
法令順守については、業界や地域によって異なる要件があります。SOC 2はクラウド事業者の統制基準で、HIPAAは医療系の個人情報保護規制です。自社の業界や扱うデータの性質に応じて、適切なコンプライアンス要件を満たしているかを確認し、必要に応じてベンダーの証跡(監査報告書やBAAなど)を取り寄せて審査してください。
Embedding生成に必要なAIモデルの選定
ベクトルDBを活用するためには、文書を数値ベクトルに変換するEmbeddingモデルが必要です。このモデルの選定は、検索精度とコストの両面で重要な要素となります。
代表的なEmbeddingモデルとして、OpenAIのtext-embedding-ada-002、Hugging Faceのsentence-transformers、Cohereのembed-english-v3.0などが挙げられます。これらのモデルは、それぞれ異なる特徴と強みを持っており、用途に応じて適切に選択する必要があります。
日本語の文書を扱う場合は、日本語に特化したEmbeddingモデルの利用を検討してください。例えば、Hugging Faceのcl-tohoku/bert-base-japanese-v3や、LINEのline-corporation/japanese-large-lmなどが利用可能です。これらのモデルは、日本語の言語特性を理解したEmbeddingを生成するため、検索精度の向上が期待できます。
モデルの選定においては、精度、速度、コストのバランスを考慮する必要があります。高精度なモデルは検索精度を向上させますが、処理時間とコストが増加する傾向があります。一方で、軽量なモデルは処理速度とコストの面で有利ですが、精度が低下する可能性があります。自社の要件(検索精度、応答時間、予算など)に応じて、適切なモデルを選択してください。
また、モデルの更新や改良も継続的に行う必要があります。Embeddingモデルは定期的に改良されており、新しいモデルの利用により検索精度の向上が期待できます。四半期に一度程度の頻度で、モデルの更新や同義語辞書の改良を検討してください。
- 効果の差は前処理で決まる:適切なチャンク化とメタデータ付与
- 検索は「意味検索+キーワード」のハイブリッドを基本に
- 評価は実際の問い合わせで数値化:Top-kの再現率や人手修正時間
- モデル更新や同義語辞書の改良は四半期に一度の頻度で十分
まとめ:中小企業がベクトルDBを選ぶときの考え方と次のステップ
ベクトルDBの導入は、中小企業にとって大きな投資判断の一つです。技術的な魅力だけでなく、実際の業務改善に直結するかどうかを慎重に検討する必要があります。ここでは、導入判断のための考え方と、次のステップについて整理します。
まず重要なのは、目的を経営視点で明確にすることです。「コスト削減」「売上拡大」「顧客対応改善」「業務効率化」など、具体的なKPIを設定し、ベクトルDBの導入がそれらの達成にどのように貢献するかを明確にしてください。技術導入のための導入ではなく、業務改善のための投資であることを常に意識することが重要です。
Pinecone、Weaviate、Qdrantの3つの製品は、それぞれ異なる強みと特徴を持っています。「どれが一番優れているか」ではなく「どれが自社の要件に最も合うか」という視点で選択してください。審査・運用の安心感を優先するならPinecone、検索体験の作り込みやAPI表現力を重視するならWeaviate、コスト最適化と展開の自由度ならQdrantが実務的な初期仮説となります。
導入の進め方としては、小さなPoCからスタートし、成長に合わせて段階的に拡張することをお勧めします。最初から完璧を目指すのではなく、対象を一つに絞って2〜4週間のPoCを回すことで、投資判断が明確になります。PoCでは、実際の業務データを使用して、検索精度、応答速度、運用負荷などを測定し、期待される効果と必要な投資を定量的に評価してください。
評価指標としては「回答までの時間」「正答率」「人手修正時間」「利用率」の4つが重要です。これらが改善すれば、サポート負荷の軽減や商談スピードの向上に直結し、投資対効果を明確に測定できます。また、PoCの結果を踏まえて、段階的な拡張計画を策定し、成功事例を積み重ねていくことが、長期的な成功の鍵となります。
ベクトルDBの魅力は、従来のデータベースでは実現できなかった「意味的な検索」を可能にし、蓄積された社内データの価値を最大化できることです。適切な導入と運用により、顧客対応の品質向上、営業支援の強化、社内ナレッジの活用促進など、具体的な業務改善を実現できます。
最後に、ベクトルDBの導入は技術的な挑戦であると同時に、組織のデータ活用文化を変革する機会でもあります。従来の「ファイル管理」から「意味的な検索・活用」への転換は、組織全体の情報共有と意思決定の質向上につながります。この転換を成功させるためには、経営陣の理解と支援、現場での継続的な学習と改善、適切な外部支援の活用が重要です。
次のステップのためのチェックリスト
□ 具体的な業務改善目標の設定
□ 対象業務とデータの特定
□ 技術要件と運用体制の整理
□ 適切なベクトルDBの選定
□ 2〜4週間のPoC計画の策定
□ 評価指標と成功基準の設定
□ 段階的な拡張計画の策定
株式会社ソフィエイトのサービス内容
- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応
- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援
- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上
- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い
ベクトルDBの導入について、要件整理からPoC設計、モデル・ベクトルDB選定、セキュリティ審査、運用設計まで一気通貫で伴走可能です。まずは既存ドキュメント一式での小規模検証からご相談ください。中小企業のAI導入を成功に導くため、技術的な支援だけでなく、業務改善の視点からの伴走支援を提供いたします。







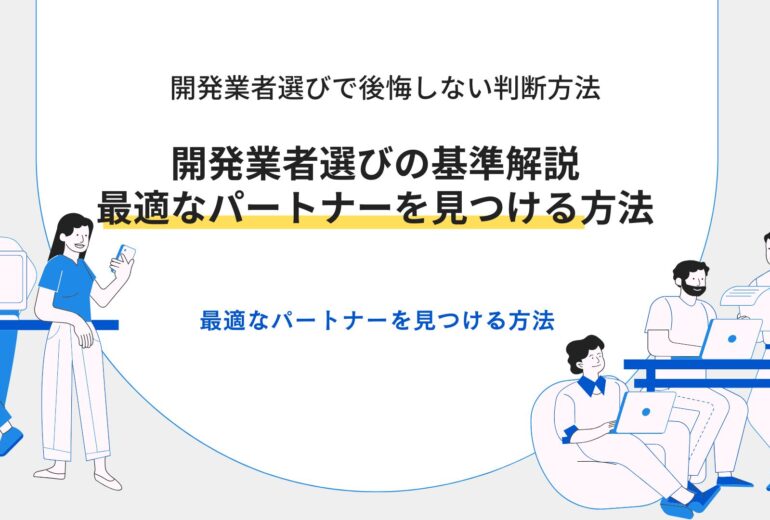












コメント